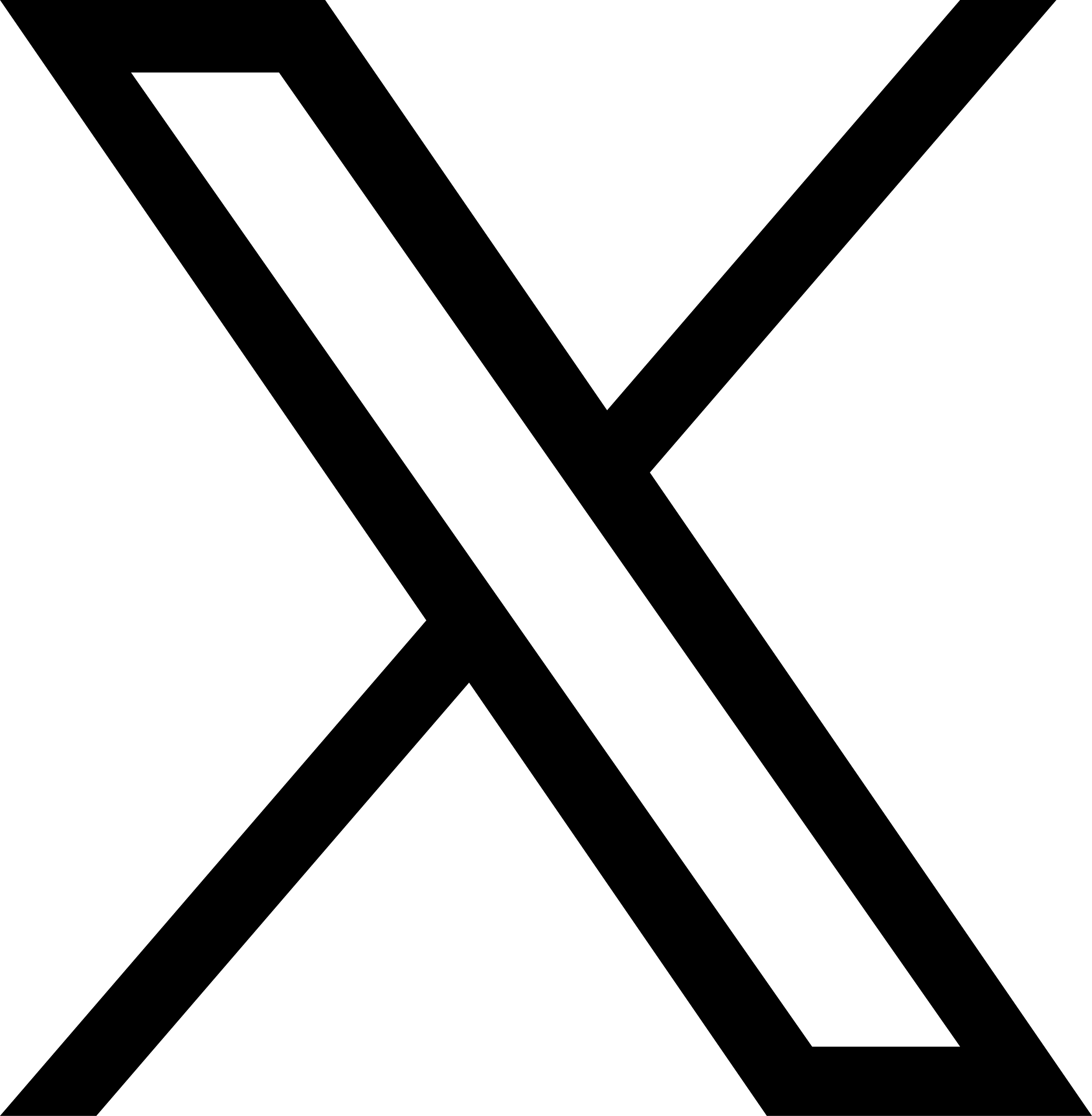就活エージェントの有用性とは?メリットから効率的な使い方まで徹底解説!
その他
CONTENTS

就活マンのエージェント利用経験について
エージェントを利用するメリット・デメリットについて
メリット①:他己分析を行ってもらえる
メリット②:自分に合った企業の紹介
メリット③:選考のフィードバックをもらえる
デメリット:「受け身」だとミスマッチが起こる
結局どんな人が就活エージェントを利用すべきか?
就活エージェントは何を基準に選べば良いのか?
就活エージェントは複数利用するべき?
就活エージェントを利用するうえでの注意点
まとめ
就活エージェントとは、就活を行う学生に向けて企業を紹介するサービスです。無料で受けることができ、サービス内容は、他己分析、業界職種の情報提供、企業紹介、選考フィードバック、内定後のカウンセリングなど多岐にわたります。
今回は様々な就活サービスを取材、研究されてきた「就活マン」こと藤井智也さんに就活エージェントの有用性についてインタビューさせていただきました!
【インタビュイープロフィール】
就活マン/藤井智也
- ・就活攻略論:https://shukatu-man.hatenablog.com/
- ・就活マンブログ:https://syukatuman-blog.jp/
- ・ツイッター:https://twitter.com/shukatu_man
累計500万PVの就活ブログ「就活攻略論」を運営。中堅大学から大手食品企業に入社した全技術をブログにて執筆している。
「就活を頑張っているけど、なかなかうまくいかない」
「サービスを利用してみたいけど、よくわからず抵抗がある」
といった方に向けて詳しく解説していきます!
就活マンのエージェント利用経験について

―就活時代に就活エージェントを利用されましたか?
藤井さん:2社使ったことがあって、もともと愛知の大学にいたので1社は愛知の就活エージェントを利用して、もう1社は関東の就職を考えていたこともあり関東の就活エージェントを利用していました。住んでいたのは愛知だったため東京のエージェントさんとは電話でやりとりしていました。
利用を続ける中で比較したところ、愛知のエージェントは微妙だったので使うのをやめてました。一方東京のエージェントには2社ほど紹介してもらいました。ただ、自分が持っていた内定先のほうがいいなと思ったのでそちらを選びました。
―利用するということに抵抗はありませんでしたか?
藤井さん:「対面?しかも無料で?」という不安はありました。利用する前は、「就活エージェントがなぜ無料なのか」という仕組みの部分をしっかりと理解していなかったので、初回面談に行くハードルは高かったですね。
―私は運営側なのでそこらへんの感覚がわからないのですが、今の学生も同じような不安を抱えている可能性は?
藤井さん:あると思います。利用者は2パターンあって①友達に紹介してもらう、②自分でネットで見つける、とあるのですが後者は情報が少ないのでおそらく不安でしょう。なので、僕の『就活攻略論』でも人材紹介のことをわかりやすくかみ砕き、実際の体験談を紹介することで利用のハードルを下げる手助けになるのではないかと考えています。
エージェントを利用するメリット・デメリットについて
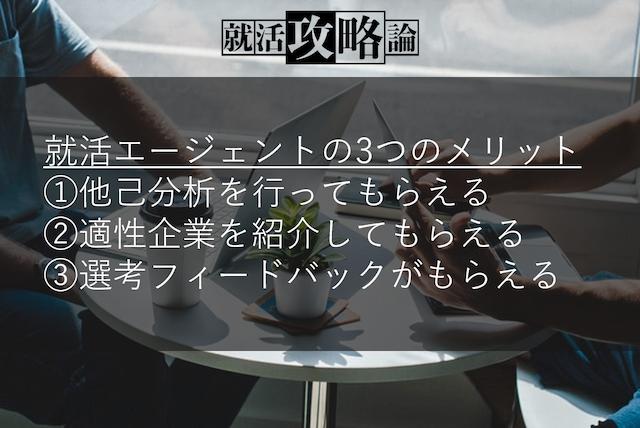
―改めて就活エージェントについて取材されてきた結果、就活エージェントを利用するメリットはなんだと思いますか?
藤井さん:大きく3つあって、①他己分析ができる、②自分に合った企業を紹介してくれる、③選考のフィードバックをもらえる、といったところでしょうか。
メリット①:他己分析を行ってもらえる
藤井さん:1つ目の他己分析は初対面の人だからこその価値があります。確かに親しい友達や家族から見た視点も重要なのですが、就活における面接は基本的に「初対面」。なのでいわゆる選考目線で自分の印象を聞けるチャンスは貴重です。
初対面のエージェントが受けた印象≒選考で面接官が受ける印象
―自分が伝えたい強みがない場合は、それが伝わるように自己PRやガクチカのエピソードを見直す必要がありそうですね。
【新卒向け】具体例から分析する相手を頷かせる自己PRのポイント
【例文・解説あり】ガクチカ(学生時代頑張ったこと)の書き方とポイント!
メリット②:自分に合った企業の紹介
藤井さん:2つ目の「自分にあった企業を紹介してくれる」というメリットは企業そのものよりも「紹介理由」にあると思います。「なぜここを紹介したのか」という疑問を突き詰めていくと、自分に合う企業の特徴を見出すことができます。そうすると後から自分で探すことも可能なので企業選びにおいてかなり役立ちますね。
―たしかに、学生さんも紹介された理由が明確だと納得して選考に進めますよね。
藤井さん:はい、逆にここを理由をしっかり伝えられないエージェントは利用しないほうが良いと思います。
例えになってしまいますが、良く売れる美容師さんはお客さんに「なぜこの髪の切り方なのか」「なぜこの乾かし方なのか」といった細かい部分を説明してくれます。するとお客さんは納得感をもってサービスを受けることができるのができるんですね。どんなサービスもそういった誠実な対応が求められるんじゃないかなと。
メリット③:選考のフィードバックをもらえる
藤井さん:3つ目の選考のフィードバックはかなりメリットが大きいですね。普通に就活をしていると受かった理由や落ちた理由は絶対わからないですし、あくまで自分の推測でしか判断できないんですよね。その中でもよくあるのが、落ちた原因を自分は原因だと認識していないことなんです。
―落ちた原因を「原因」と認識していないケースとは具体的にどんなものでしょうか?
藤井さん:例えば、相談に乗る学生さんでいらっしゃるのが志望動機が不十分な場合です。本人はちゃんと書いているつもりでも企業からすればダメということを気づくことができるのとできないのとでは大きな差があります。
―気づかないまま就活するより、気づいて修正したほうが時間効率も良いですね。
デメリット:「受け身」だとミスマッチが起こる
―エージェントを利用する最大のメリットについてご説明いただきましたが、逆にデメリットはなんでしょうか?
藤井さん:担当者の良し悪しが判断できないといわゆる「受け身の就活」になってしまうことでしょうか。先ほども述べたようにサービスによっては最良の選択肢でない求人を紹介されることもあります。その際に紹介されたものをすべて鵜呑みにすると、後で適正が合わないといった事態が起きます。
結局どんな人が就活エージェントを利用すべきか?

―先ほどのデメリットは人によるかと思います。結局のところ、どんな人なら就活エージェントを利用しても良い、またはするべきでしょうか?
藤井さん:就活が上手くいっていない、けど受け身ではなく「攻めの就活」ができる人が利用すべきですね。
先ほどの3つのメリットも能動的に活かすことができる人は是非利用するべきかなと。例えば他己分析や選考のフィードバック次の面接に活かそうだったり、紹介理由を自分の企業選びに活用しようだったりですね。
一方ずっと受け身の就活をしている人だと「うまくいかない理由」「企業が合わない理由」をすべて人のせいにしてしまう傾向があります。例えば「とりあえずどこか受かればいいかな」と考えている人はいざ自分に合わないとエージェントのせいにしてしまいますし、その後の転職を考えるときも同じ不幸を招きます。
―なるほど、例えば頑張りたい想いはあるけど、なかなか行動に結果が出ないという人はいかがですか?
藤井さん:その場合は利用しても問題ありません。あくまで「攻めの就活」というのは助言や知識を活かそうとする意志があるか否かなので、むしろ就活へのモチベーションがある人は積極的に利用すべきですね。
就活エージェントは何を基準に選べば良いのか?

―就活エージェントってJobSpring以外にもたくさんありますが、学生さんはどういうふうに選べば良いでしょうか?
藤井さん:①口コミの評判が良いところと②規模でしょうか。
就活エージェントは一回体験しないとわからないので、参加した人の評判は確認すべきですね。例えば、SNSでの口コミや複数のサービスをレビューしているサイトなどが参考になります。
その次に規模なのですが、ある程度求人数を保有しているサービスでないといくら良いエージェントだったとしても限られた求人の中から学生に合うものをあてるしかないため、利用者としては選択肢が狭まる印象です。
就活エージェントは複数利用するべき?
―では、どこのサービスが自分に最適かを見極めるためにも複数利用すべきでしょうか?
藤井さん:そうですね。必ず2社は見ることをおすすめします。なぜなら同じサービスでも担当者によって質が異なるからです。基準通りに選んでも、もし自分の担当が悪かったら「こんなものなのか」と疑問を持たずに継続してしまいますが比べることで担当があってないと気づくことができます。
就活エージェントを利用するうえでの注意点
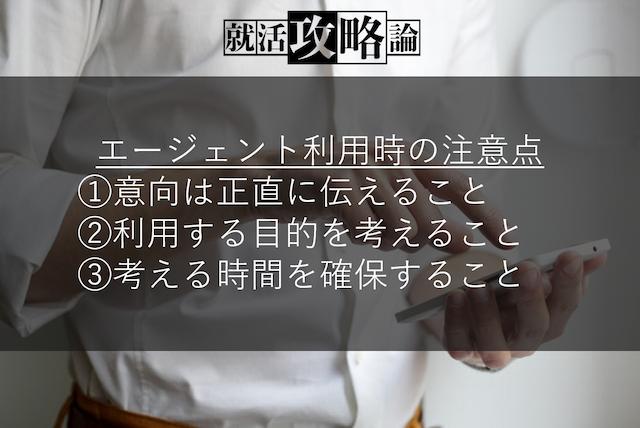
―利用するエージェントを決めた後も気を付けてほしいことはありますか?
藤井さん:自分の性格や希望と全く異なる企業を紹介された場合は気を付けたほうがいいですね。就職先を決めるのはあくまで自分なので「嫌だな」とおもったらはっきり伝えることは大事です。もちろん「せっかく内定までサポートしてもらったのに」という申し訳なさがあってもここは妥協してはいけません。
またこれは就活に限らずあらゆることにいえることなんですが、サービスを利用する目的を明確にするということ、そして行動する時間と同じくらい考える時間をとることでしょうか。
先ほどの「攻めの就活」にも関連するのですが、3つのメリットを把握したうえで「何を得るのか」を意識した行動ができると良いですね。
―これは企業説明会にいくときなんかも使えますよね?
藤井さん:はい!例えば今回の「説明会では競合他社とは違う点を徹底的に洗い出してみよう」といった具合ですね。
またこの目的を明確にした行動を行うためには、とにかく「考える時間を確保する」習慣を身に着けるべきだと思います。結局目的を明確にする際も、あまり考えずに行動に移すとそれも受動的な就活に陥ってしまうので。
まとめ

就活が長期化、複雑化してきている昨今だからこそ就活エージェントを利用する方が増えています。今回の記事の要点を以下にまとめましたので、ご利用の際の参考にしてみてください。
・メリット:①他己分析、②企業紹介、③選考FB
・デメリット:「受け身」だと企業のミスマッチが起こる
・頑張っているけど上手くいかない人には効果絶大
・選ぶ基準:①口コミと②規模感
・注意点:①正直に伝える、②目的を明確化、③考える時間をつくる
―逆にエージェント側に意識してほしい点はありますか?
藤井さん:やはり、学生にとって大きなメリットである①他己分析を行う、②自分に合った企業を紹介する、③選考のフィードバックを行う、の3つを最初の面談できちんと説明してあげることだと思います。
結構、就活エージェントさんっていきなりヒアリングを始める印象でして、それが学生のモチベーションを下げる要因にもなるんじゃないかと。人って目的が明確じゃないとモチベーション高く行動できないので。しっかりとそこを共有したうえでヒアリングするとサービスも受けやすいと思います。
―JobSpringもより学生さんに寄り添ったサービスにできるよう努めて参ります…!本日はありがとうございました!
藤井さん:ありがとうございました!
RANKING
人気記事ランキングTOPIC
新着記事