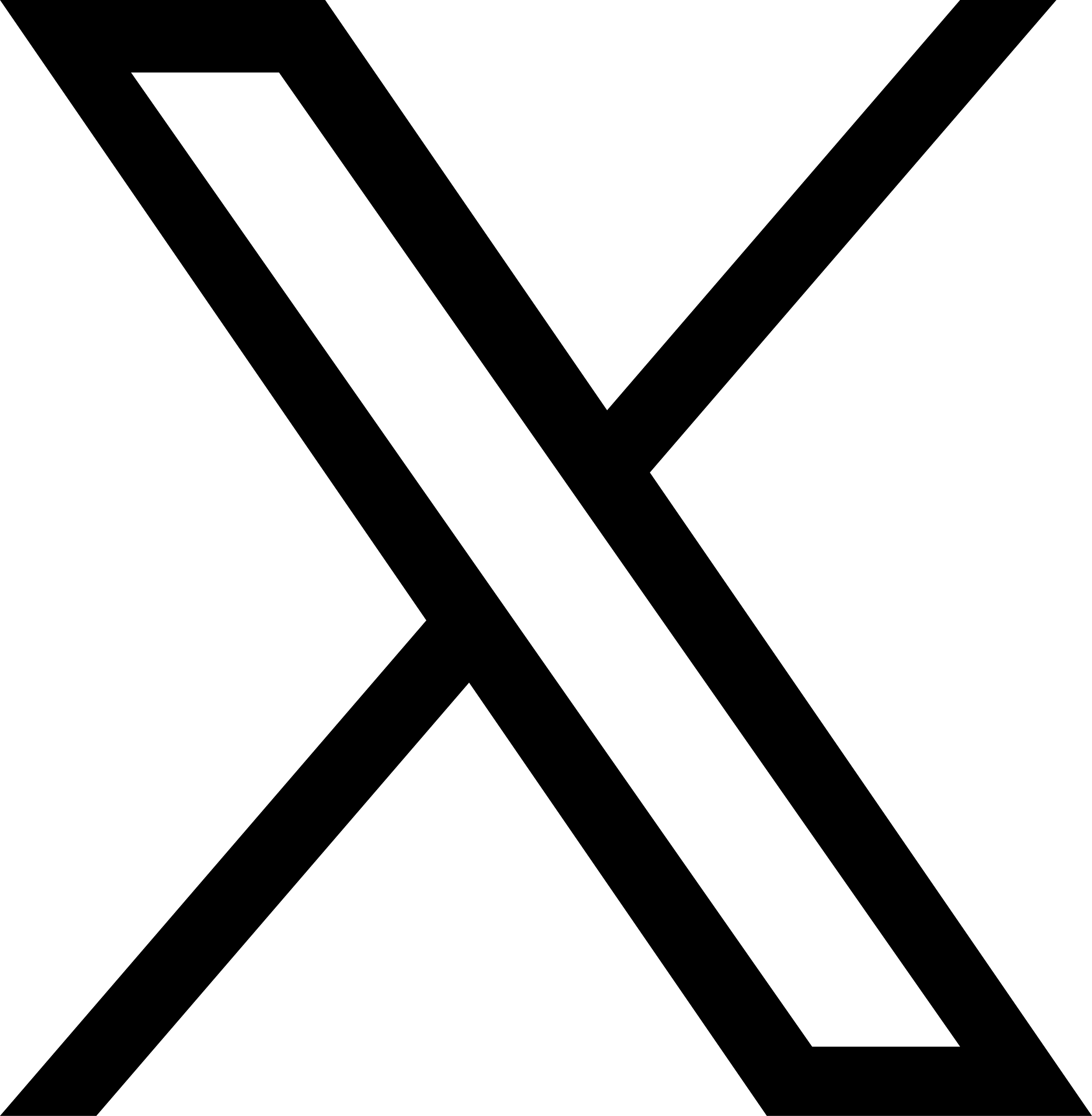【徹底解説】ケース面接をわかりやすく解説!基礎的なフレームワークから身につける実践学習 -応用対策編-
面接
CONTENTS

ケース例題①:フェンシング全国大会の観客人数を増やすには?
A. 前提条件と課題の確認
B.現状の分析
C.フレームワークの利用とボトルネックの特定
D.対応施策(打ち手)の提案と評価
ケース例題②:スピード違反の数を減らすには?
A. 前提条件と課題の確認
B.現状の分析
C.フレームワークの利用とボトルネックの特定
D.対応施策(打ち手)の提案と評価
難易度の高いケース面接対策のコツ
フレームワークに縛られない
自分の経験を頼りに現実に即した分析をしよう
応用練習問題:飛行機を利用する旅行客の満足度を上げるには?
まとめ
今回は基礎対策編に引き続きケース面接の応用的な対策について解説していきます。フレームワークだけにとらわれない独自の発想力や提案を考案するための力を身に付けていきましょう。
応用編では下記の3問を例題としてより柔軟な発想力を磨いていきます。基礎編よりも少し難しい内容となっていますので、ぜひ頑張ってみてください!この記事を通してケース面接を得意分野にしましょう!
【徹底解説】ケース面接をわかりやすく解説!基礎的なフレームワークから身につける実践学習 -概要編-
【徹底解説】ケース面接をわかりやすく解説!基礎的なフレームワークから身につける実践学習 -基礎対策編-
ケース例題①:フェンシング全国大会の観客人数を増やすには?
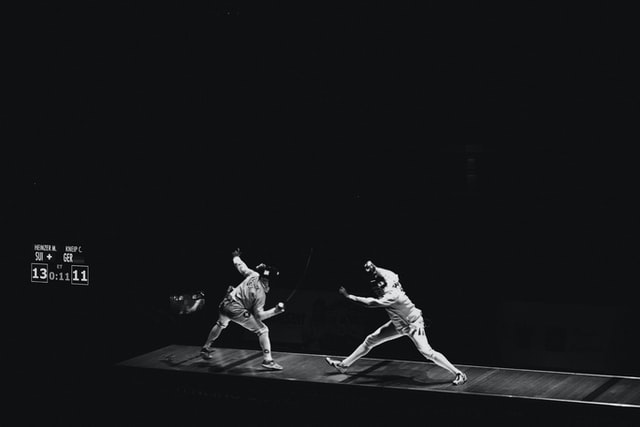
【ストーリー】
あなたの友人はフェンシング協会の会長です。彼はフェンシングの全国大会の常連であり、日本ではまだまだマイナースポーツであることに疑問を感じています。あなたは友人からフェンシングを日本でもメジャースポーツにしていきたいと言われ、相談に乗ることにしました。あなたならどのように競技人口を増やすでしょうか?10分で考えて説明してください。
A. 前提条件と課題の確認
今回のケースはフェンシング協会の友人から日本におけるフェンシングの競技人口及び知名度をあげて欲しいという相談です。観客人数の定量目標については示されておらず、非常に抽象度の高い相談ですがフェンシングという競技自体がどのような関係者によって構成され、どうすれば多くの人に魅力を伝えられるかという分析をすることから始めると良いでしょう。
ここではフェンシングプレイヤーを2週間に1回以上する人というように定義づけ、プレイヤーの人口を増やすことで相談者の目標を達成することを目指します。
B.現状の分析
それでは今回のケースの現状分析を行っていきます。ストーリーの説明で「日本でフェンシングをメジャースポーツにしたい」ということが明確に示されていますので、今回打ち手施策のターゲットになり得るのは日本人全員となります。しかしながら、もちろん全く興味がない人などもいるわけですから、プレイヤーとなり得る日本人を年齢別に分けて、それぞれ考えていきましょう。
①若年層(子供、学生等)
様々なことに対して吸収力が高い年齢層であることから、競技自体の魅力に気づいてくれる可能性が高いといえるでしょう。
2008年の北京オリンピックで太田選手が金メダルを獲得したことなど、フェンシングについてニュースで少し聞いたことがあったり、競技自体を知っていたりする可能性が高いため、アッパー世代よりも抵抗感なく競技に参加してくれそうです。フェンシングは防具が高いため親の経済力や学校自体に設備があるかどうかといった外的要因も影響してくるでしょう。
②社会人層
少し経済的にも余裕があり防具などに手を出しやすい世代だと考えられます。フェンシングについてもオリンピックをある程度成長した時に観戦していれば、社会人として新たなスポーツを始める際の選択肢の一つになるかもしれません。加えて学生に比べて意思決定の自由度が高く、様々な団体に個人的に足を運ぶことも可能になります。観戦やイベントへの参加でプレイヤーとして取り込むことができるかもしれません。
C.フレームワークの利用とボトルネックの特定
今回は二つのフレームワークを駆使して、ボトルネックを特定し打ち手策の提案へとつなげます。今回利用するフレームワークは基礎編でもおなじみのAIDMAと年齢と性別のマトリックスセグメンテーションです。
まずAIDMAを使ってある人がフェンシングのプレイヤーになるまでの行動を分解してみましょう。基礎編でも紹介したAIDMAは元々消費者の購買決定のプロセスを分解するものですが、今回はMemoryを省略してより簡単に活用してみましょう。
| AIDMA | 各段階における分析 |
|---|---|
| Attention 注意や気づき |
フェンシングという競技は選手は少ないものの、知名度が低いわけではありません。 しかしテレビでの試合の放映は他のスポーツに比べて少ないため、 マスメディアを通じた宣伝も認知させる機会となり得るのではないでしょうか。 |
| Interest
興味 |
競技に対するプレイヤーとしての興味は競技の実体験を基にしたものと外的な印象によって生まれると考えられます。 フェンシングを実際に体験する機会はほとんどないと考えられるので、 そういう機会を作るのも興味を持ってもらう一つの方法でしょう。 また、オリンピックなどで日本人選手が活躍しているところを見ると応援したくなるという心理が働きますので、 現存の選手を強化し、国際大会における日本のプレゼンス向上も間接的に興味を持たせる要因と言えるでしょう。 |
| Desire
欲求 |
プレイヤーとして競技に参加したいという欲求は上記の興味をベースに起こると考えられます。 そのため、いかに興味を持ってもらう活動を広い範囲で実施できるかが重要でしょう。 |
| Action
行動 |
実際にプレイヤーとして競技に参加するには団体への所属(部活や社会人団体など)、 防具の準備、練習場所の確保など多くのプロセスがあります。 今回は上記3つのことを考慮しつつ、打ち手を考えていきましょう。 |
さて、AIDMAを用いた分析は上記になりますが、今回はそれに加えて年齢と性別のマトリックスを用いてさらにターゲットを絞ります。年齢層については前提条件確認時よりも詳しく分けています。
| 年齢と性別 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 0~20歳の若年層 | 運動意欲がある人の割合が多く、 競技を始めるのにも時間的な余裕もあります。 |
女性の場合も男性と同様運動意欲がある人の割合が多く、 競技を始めるのにも時間的な余裕もあります。 |
| 20~40歳の社会人層 | 金銭的な余裕が少し出てきますが、 時間的な制約があります。 |
新しいスポーツを始めるとなるとこちらも同様に時間的な制約があるでしょう。 また、男性と違うポイントとして出産など 様々な要因によって男性以上に時間がなくなってしまう場合もあります。 |
| 40~65歳の中高年層 | 金銭的な余裕はありますが、 体力的に厳しいものがありなかなか新しいスポーツを始めるのは難しいでしょう。 |
こちらも体力的に厳しいものがあり なかなか新しいスポーツを始めるのは難しいでしょう。 |
| 65歳~の高齢層 | 瞬発力などの衰えから、あまりフェンシングをはじめる適齢とはいえません | 男性と同様にあまりフェンシングをはじめる適齢とはいえません。 |
上記から、0~40歳の男性を中心としたアプローチが最も効率よくプレイヤーを増やすことができそうです。上記の表はBの制約条件と一部かぶるところもありますが、整理するという意味合いもかねてより詳しくまとめると説明をする時に便利です。
D.対応施策(打ち手)の提案と評価
これまで前提条件と分析をしてきました。以下にそれらを踏まえた打ち手施策をリストアップしたので確認していきましょう!
1. 学校においてフェンシングの体験授業および部活への導入を検討する
これは年齢マトリックス上の若年層(0~20歳)をターゲットとした打ち手策です。小中高の特別授業やホームルームなどでフェンシングの講師(大学生や社会人ボランティアなど)を招いて、実際に子供たちに体験してもらうというような策です。その際、参加者に負担を背負わせることなく純粋に競技としてフェンシングを楽しんでもらうため、防具などは事前に用意し環境を整えておきます。
また、保護者会などと同じタイミングで行うことで父兄の方々にも競技について知ってもらい、部活としての検討も促進します。
2. 大人向けの本格的な講習会を企画する
こちらは年齢マトリックス上の大人層(20~40歳)をターゲットとした打ち手策です。元オリンピック選手や国体選手を会場に招き、自身のスポーツキャリアでの経験などを語ってもらう講演会と実体験型のイベントを同時に開催します。実際にプレイヤーとして参加することにあまり気が進まない人も、講演会で直接トップアスリートからの話を聞くことで競技自体のファンになってくれる可能性があります。
3. フェンシングに関連するメディアコンテンツを作成する
年齢層にかかわらず、フェンシングに誰かが興味を持てばその友人や家族に伝播して伝わっていきます。そのため宣伝効果を最大限高めるためには年齢問わず楽しめるスーパープレー集の映像やわかりやすいルール説明映像など様々なコンテンツを通じてフェンシングの魅力をアピールするべきです。そうすることで直接的にフェンシングへの興味を煽るだけでなく、間接的に人を伝って魅力を伝えることができます。
ケース例題②:スピード違反の数を減らすには?

【ストーリー】
年々、自動車を利用する人が世界中で増加しています。それに伴い法定速度を超過するスピード違反などの交通違反が増え、日本の警察は頭を抱えています。警視庁の友人からコンサルタントであるあなたのもとにどのようにすれば交通違反を減らせるかと相談がきました。あなたならどのようにスピード違反を減らすでしょうか。10分でできるだけ具体的に考えて説明してください。
A. 前提条件と課題の確認
今回は違反者数の増加を懸念した警察庁の友人から違反者数を減少させるにはどうすれば良いかという相談です。実際日本ではスピード違反自体の検挙件数は減っているものの、交通違反は劇的な改善と言えるほど減っているわけではありません。
今回は交通違反を分解し、交通違反が起こる原因や種類などをある程度絞って打ち手施策を考えていきます。
B.現状の分析
一口に交通違反といっても様々なものがあります。以下に主な交通違反をまとめました。
- 酒酔い運転(酒気帯び運転)
- 携帯電話使用等
- 無免許運転
- 妨害運転
- 速度超過
- 信号無視等
このほかにも様々な違反がありますが、今回限りある時間の中で考えるのは違反数が特に多い速度超過や携帯電話の使用、そして深刻な被害につながる酒酔い運転と妨害運転の4つにします。
(1)速度超過
速度超過は法定速度を上回って車両を走行させる違反ですが、この速度制限については国道によって異なる場合があり勘違いなどからも発生しやすい違反です。交通違反の中では検挙率が最も多く、この違反を低減させることができれば大きく交通違反数を改善できるでしょう。
(2)携帯電話の利用等違反
こちらはスマートフォンの普及に伴って検挙率が上がった携帯電話の操作と運転を同時に行う「ながら運転」などが対象となる交通違反です。若年層の違反数が多く、一歩間違えば甚大な被害となります。こちらの違反は違反の重大さに人々が気づいていないような印象があります。少しだけならいいだろうと言った慢心をどのように改善するかが打ち手策を提案する上で重要でしょう。
(3)酒酔い運転
飲酒運転は最も危険な違反で、死亡事故に絡むケースが非常に多い違反です。人的な被害はもちろんですが、公共物の破壊など経済的な損失も大きい違反と言えます。こちらは誰しもが違反であると知っている中、運転者が故意に飲んで運転している点から非常に悪質で同情の余地がない違反でしょう。
飲酒をするかどうかの意思決定において運転者が飲まないようにするには厳罰化の他に例えば「運転者カード」など周りの人がその人にお酒を飲ませては行けないというように伝達する方法などが考えられるのではないでしょうか。
(4)妨害運転
煽り運転などの妨害運転が2020年6月30日から妨害運転罪の創設とともに厳罰化されており、こちらも重大な事故を引き起こす原因として捉えられています。社会的関心が高い状況においてこの妨害運転を抑えることができれば、交通違反に対しての意識を向上させることができ違反を減少させることにつながるでしょう。
C.フレームワークの利用とボトルネックの特定
さて、対象となる交通違反の分解をした時に何がそれらの原因となるかを詳しく見ていきましょう。ここでは「原因・結果」フレームワークと「内外分解フレームワーク」を利用してボトルネックを特定します。
| 交通違反 | 原因 | 結果 |
|---|---|---|
| 速度超過 | ルールを知っていながらも時間短縮やスリルの追求によって速度を出してしまう。 | 交通量が多い交差点などでの事故の発生につながる。 |
| 携帯電話の利用等違反 | 重大さが理解できていない人がほとんどであり、 なんとなく使ってしまうことも多いのではないか。 また、ハンズフリーの電話機能などがついていない車種も日本では多く見受けられる。 |
前方不注意による人身事故、巻き込み事故など様々な事故が誘発される。 |
| 酒酔い運転 | 個人の判断ミスや周りからの圧力など運転する以前の問題である。 社会全体として飲酒運転を許容しない雰囲気作りが必要。 |
重大な交通事故を引き起こすことがほぼ確実で、 そもそも運転を諦める必要がある。 施設や公共物の破壊、人への被害、同乗者への恐怖感など与える被害が甚大である。 |
| 妨害運転 | 瞬発力などの衰えから、あまりフェンシングをはじめる適齢とはいえません | 別の運転者への恐怖感や輸送機能の低迷など社会的に嫌悪されるものである。事故や渋滞の誘発につながる。 |
内外分解フレームワーク
さて、上記の原因と結果の分析における原因部分を内的な要因と外的な要因に分けてさらに詳しく見ていきます。
| 交通違反 | 内的発生要因 | 外的発生要因 |
|---|---|---|
| 速度超過 | 時間短縮、スリルの追求、ストレス発散等 | 時間的切迫感(予定の時刻に間に合わないなど) |
| 携帯電話の利用違反など | 運転中の暇つぶしや連絡など | 運転者への連絡等 |
| 酒酔い運転 | 気の緩み、状況判断能力の欠如「一杯だけなら大丈夫」といった思い込み | アルコールハラスメントや気の緩みによる飲酒の推奨 |
| 妨害運転 | 精神的なストレスの発散等 | 運転者への煽り行為、悪ふざけの助長等 |
上記のようにそれぞれの交通違反は二つの側面から解決する必要がありそうです。
D.対応施策(打ち手)の提案と評価
さて、これまでのことを踏まえて対応施策の提案をしていきます。
1.移動式オービスの設置台数の増量
現在スピード違反を取締る機材としてオービスが導入されており、無人でも的確にスピード違反を捉えられるため重宝されています。しかし、導入数については当初より増えているものの、諸外国に比べればまだまだと言えます。導入数を増やすことでそれだけ人々に対してスピード監視を行っているというアピールとなりますし、見られているという意識を植え付けることで、潜在的にスピード違反をする運転者を減少させることにつながるでしょう。
2.酒気チェッカーの導入
車に搭乗する際にエンジンをかけるために呼気を吹き込む装置を取り付け、その呼気に含まれるアルコール量が基準値を下回っていれば初めて運転できるような仕組みを提案します。これは航空機のパイロットが行うアルコールチェックのようなもので、その検査をパスしなければ運転できなくしてしまうのです。こうすることによって、飲酒をしてしまう外的な要因と内的な要因があってもどちらにも効果的に対処することができます。
3.自動運転技術の向上と普及(官民連携)
少し突飛な提案ではありますが、交通違反は人の判断ミスや意思決定によって起こります。そのため、その部分を人から取り上げることで根本的に違反をなくすという提案です。自動運転技術は現在日本では段階的に承認されており、一部の機能で自動運転が認められる場合もあります。道路交通法など法律的な立て付けやフェールセーフなソフトウェア設計など多くのことが求められますが、人為的なミスを改善することで大幅な違反数減少が見込まれるでしょう。
難易度の高いケース面接対策のコツ

フレームワークに縛られない
ケース面接の対策をしている多くの人はフレームワークへの当てはめやフェルミの結果に頼って自分のアウトプットをしようとしますが、それはおすすめできません。そもそもケース問題とはフェルミ推定の精度やフレームワークにうまく当てはめられているかをみているわけではなく、本人の思考過程をチェックしているに過ぎないからです。
もし、何か面接官からフレームワークで拾いきれない漏れを指摘された時、あなたはどう対応するでしょうか?全く見当もつかないようなことをクライアントから質問された時あなたは黙ってしまうのでしょうか?おそらくその時あなたがしっかりと思考の過程を相手に明らかにした上で議論を進めていればそんな質問は飛んできません。なぜならそのような場合、あなたはクライアントとコミュニケーションを取りつつ、漏れがないように確認しているからです。フレームワークだけを使って話してしまうと、灯台下暗しといったように根本的な前提条件を忘れてしまうことが多くなります。
ケース面接はあくまで成果はもちろんのこと、あなたの態度、コミュニケーション能力、身嗜みなど全てのことが同様に評価されます。成果ばかり気にしてクライアントに失礼な態度を取ってしまえば、それでおしまいです。ぜひ、ケース面接に臨むときは謙虚にかつ、イレギュラーな質問に対してもその質問の本当の意図を見抜くことを意識して頑張ってみてください!
自分の経験を頼りに現実に即した分析をしよう
より現実的な提案をするには自身の経験を元にした話を展開することが有効です。例えば、コンビニでのバイト経験で感じたこと(フードロスや発注の難しさ)や飲食店の接客業ならば、売り上げを改善するためにより良いサービスを提供できないかといったことも実体験に基づいて話すことができます。そのようなあなたのオリジナリティあふれる提案こそ説得力があるのです。
応用練習問題:飛行機を利用する旅行客の満足度を上げるには?

【ストーリー】
各航空会社はフライトの時間を快適にし、他社と差別化を図ることで自社の顧客満足度をあげリピーターを増やしたいと考えています。あなたはある航空会社からサービスの抜本的な改善をしたいと相談を受けました。航空会社のサービスの満足度を上げ、航空会社の売り上げを伸ばすにはどのような施策が考えられるでしょうか?10分でできるだけ具体的に考えて説明してください。
以下A~Dの流れで自分なりに整理して友人や家族に説明してみましょう!
- A. 前提条件と課題の確認
- B.現状の分析
- C.フレームワークの利用とボトルネックの特定
- D.対応施策(打ち手)の提案と評価
まとめ

フレームワーク、フェルミ推定などケース面接においては様々な知識や論理思考力が必要とされます。より効果的な施策を提案するためには何度も練習を繰り返し、ケース問題を解くことに慣れていかなければなりません。以下に今回の応用編のポイントをまとめましたので確認してみてください!
【今回の記事のポイント】
- ✔ フレームワークから脱却し柔軟性を高める
- ✔ 前提条件をしっかりと詰め切り、独創性のある提案も果敢にしていく
- ✔ コミュニケーションを忘れず、クライアント(面接官)との良い関係構築を目指す
上記のことを意識すれば、あなたはきっとケース面接を乗り越えられるはずです!繰り返し練習をすることで応用力をさらに磨いていきましょう!
RANKING
人気記事ランキングTOPIC
新着記事