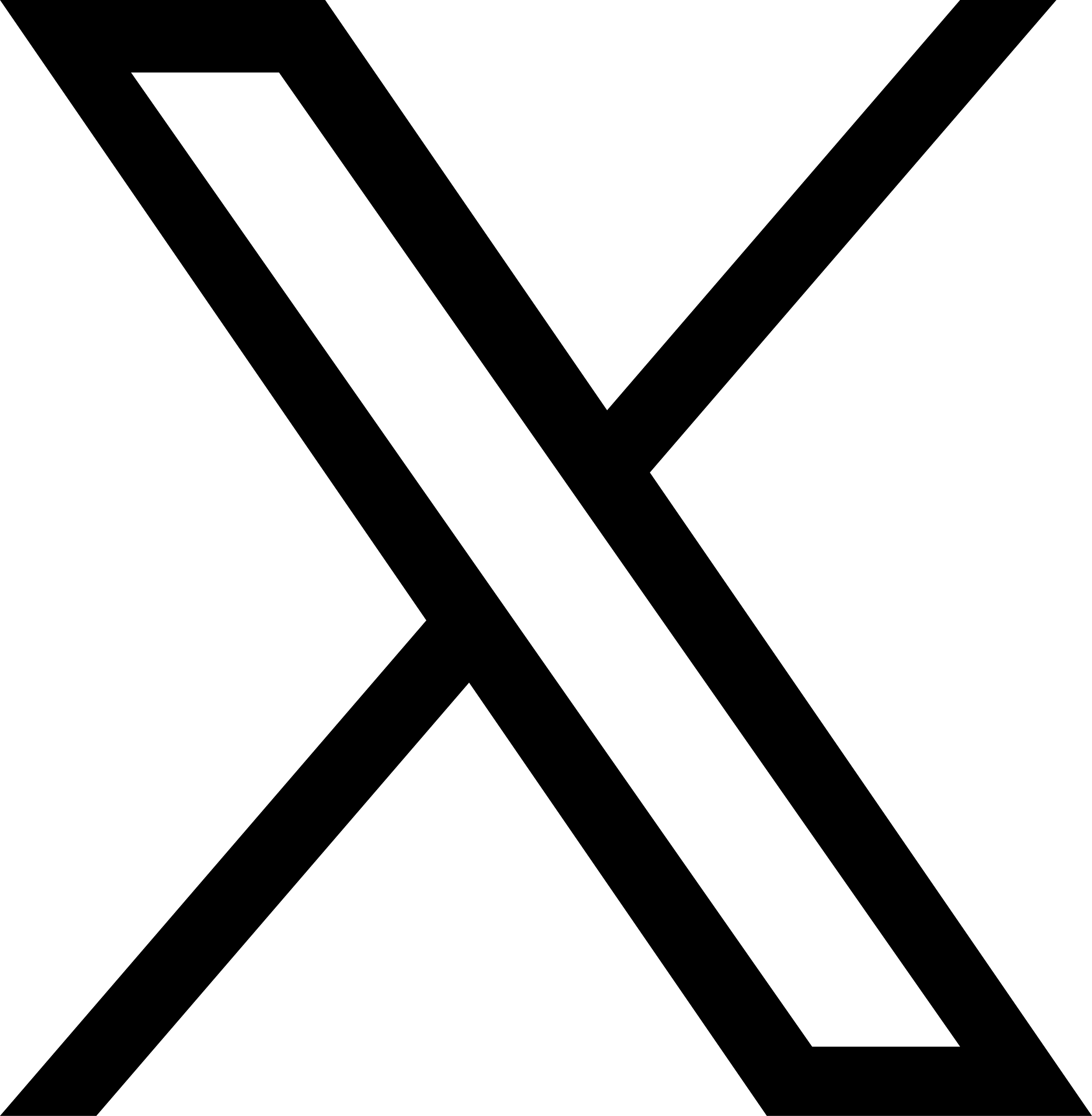【徹底解説】ケース面接をわかりやすく解説!基礎的なフレームワークから身につける実践学習 -基礎対策編-
面接
CONTENTS

ケース頻出の問題タイプを知ろう!
ケース問題タイプの分類
1.【解答例つき】「企業・社会ケース」の練習問題
A. 前提条件と課題の確認
B.現状の分析
C.フレームワークの利用とボトルネックの特定
D.対応施策(打ち手)の提案と評価
2.【解答例つき】「 個人問題ケース」の練習問題
A. 前提条件と課題の確認
B.現状の分析
C.フレームワークの利用とボトルネックの特定
D.対応施策(打ち手)の提案と評価
覚えておきたいケース面接対策の3つのコツ
①解決する問題のボトルネック(根本)を確認する
②前提条件を詰めて、土台をしっかりと作る
③結論は明確に
【実際に解いてみよう】ケース面接の練習問題
まとめ
今回は概要編に引き続きケース面接の基礎的な対策について解説していきます。ケース面接の対策をする上で重要な考え方であるフレームワークや問題を分解することでより効果的な解決方法(打ち手策)を見つけ出す手法などをまとめて解説します!
【徹底解説】ケース面接をわかりやすく解説!基礎的なフレームワークから身につける実践学習 -概要編-
ケース頻出の問題タイプを知ろう!

まず問題に取り掛かる上で重要なのはその傾向を掴むことです。ケース面接で問われる問題の傾向を掴むことによって、より効率的かつ効果的な対策を展開できます。
以下では多くの企業で頻出しているケース問題をいくつかのタイプに分けて紹介していきます。
ケース問題タイプの分類
ケース問題はその問題を解くことによって達成できる目的や方向性によっていくつかの種類に分類することができます。
そのうち企業の面接で頻出するのは、社会に対してインパクトを与える公共事業などをテーマにしたものや店舗や商品の売り上げを高める、市場規模を推測することを題材にしたものです。今回それらを多くの人を対象にするケース問題として、「企業・社会ケース」というように分類しておきます。
そして、もう一つとしては友人に何かの魅力を伝えるにはどうすればいいかといったような個人の趣向を考慮した上で説得するようなテーマの問題であるものですが、今回はそれを「個人問題ケース」と呼ぶことにします。
上記2つの種類のケース問題では問題解決までのアプローチが異なりますので、それぞれ以下の例題を元に解説していきます。
1.【解答例つき】「企業・社会ケース」の練習問題

まず初めに「企業・社会ケース」の問題を見ていきましょう。題材は「スポーツの国際大会のボランティアを増やすには?」という公共事業の提案(社会の効用追究)をテーマにしたものになります。
【ストーリー】
2021年夏、東京でスポーツの国際大会が開催されることになりました。あなたはコンサルタントとしてボランティアの人数を増やすにはどうすれば良いか東京都から相談を受け、解決策を提案することになりました。ボランティアはアルバイトとは違い、給料は発生しません。(交通費のみ一律1500円支給) このような状況下でボランティアを増やすにはどのような方法が考えられるでしょうか。7分で考えて説明してください。
A. 前提条件と課題の確認
今回はあなたはコンサルタントとして、クライアントである東京都からスポーツ国際大会のボランティア人数についての相談を受けています。
今回のケースの目標はボランティアの人数を増やすことであり、予算制約(大会運営にかける予算)は具体的に示されていません。そのため、今回はできるだけコストを抑えて利益を上げるという発想ではなく、必要人数を集めるためにいくらかかるか概算し、クライアントである東京都にボランティアを集める上での判断指標を提示することが最終目標です。必ずしも我々が相手の損益を勘案しすぎる必要がないということを頭に入れましょう。
しかしながらアルバイトとの違いが説明されていることからあまりお金をかけたくないということは想像できますので、通常人を集めやすい金銭的なインセンティブ(※1)の代わりとなるような代替的なインセンティブを与えることが本質的な目標だとわかります。
(※1)人に特定の行動を促すような魅力的なもの(お金や社会的名誉など)
B.現状の分析
それでは今回のケースの現状分析を行っていきましょう。まずボランティアを行ってくれそうな人を今回のターゲットである日本人から絞り込んでいきます。分析を行うときは制約を整理し、一つ一つ自分の中で前提条件を組み立てていくと論理的な話でまとめられます。
(1)地理的な制約
まず開催地が東京であり、無給のボランティアとして何日間も地方の人々が仕事や学校を休んで参加するというのは少し考えにくいでしょう。そのため、宣伝を行うときは母集団の人数の大きさと地理的な参加優位性から、東京を中心とした宣伝が効果的だと考えられます。となれば、後々提案する案ではまず最初に東京都のテレビ放送やエリア広告を用いた宣伝が効果的だと説明し、その後エリアを広げていくことが想像できるでしょう。
(2)年齢的な制約
一口にボランティアと言っても幅広い年齢層が参加できそうですが、今回は夏の大会ということもあり、平均気温が非常に高いことが予想されます。そのため小さな子供や高齢者の方ばかり集めてしまうと集団的な熱中症などが発生する恐れがありリスクがあります。それを避けるために、全体の目安として募集人数比を決めるとターゲットを考えやすいでしょう。
例えば5割は学生、3割が社会人、残り1割が高齢者の方というような具合です。そうすることで人数に応じた役割分担が計画の段階からしやすくなりますし、作業内容等を工夫することで熱中症等のリスクもある程度緩和することができます。
(3)能力的な制約
スポーツの国際大会ということであれば外国人の対応というのも発生することが想像できます。そのため、ある程度語学力に自信がある人の方がボランティアとしてスムーズに大会を運営できるでしょう。もちろん外国語が全く喋れなくても参加するという意思は非常に大切ですから、目標値として今回は3割~5割の人が日常会話程度の外国語を話せるということを定めておきます。
C.フレームワークの利用とボトルネックの特定
今回のケース問題ではAIDMAという考え方を使うことにします。元々、AIDMAは消費者の購買決定のプロセスを分解するものなのですが、今回はどのようにすれば人々がボランティアとして参加するという意思決定をしてくれるかということに着目して、応用的にこのフレームワークを利用します。
AIDMAはマーケティング戦略の一つとして捉えられますが、汎用性が高く人々の認知行動を分解していくことができます。AIDMAを順番に書き出すと、Attention(注意や気づき), Interest(興味), Desire(欲求), Memory(記憶), Action(行動)となります。
今回のケースにおけるボランティアに参加するまでの意思決定をAIDMAを用いて分解すると以下のようになります。
| AIDMA | 各段階における分析 |
|---|---|
| Attention 注意や気づき |
世界的にも有名なスポーツの国際大会ですので、どこかしらで聞いたことはあるケースが多いと思われます。 そのため、改めて大会の認知度を高めるということについては考えなくても良いでしょう。 |
| Interest
興味 |
ボランティアに興味を持ってくれる要因としては有名な国際大会に関わることができるという機会的な魅力と 何かスポーツに対してその人自身が感じる魅力によって誘発される意欲があると考えられます。 |
| Desire
欲求 |
上記の魅力を感じることで参加したいと考えるようになるでしょう。 |
| Memory
記憶 |
募集期間から開催までの期間が長い場合は宣伝をもう一度するなどして当事者意識を高める必要はあり。 加えて、そこで改めてボランティアを行うことを考えてくれる人も出てくるかもしれません。 |
| Action
行動 |
当日実際にボランティアとして参加する際に課題となるのは主に前述した3つの制約などが挙げられます。 それらは解決されているでしょうか。またその他の制約は考えられるでしょうか? |
D.対応施策(打ち手)の提案と評価
さて、これまで前提条件と分析、フレームワークへの当てはめを行ってきました。そしてここからはあなたの解答をまとめて施策(打ち手)の提案を行い、自分でその施策について客観的な視点で評価をしていきます。
(1)選手の講演会や交流会を行う
スポーツ選手の中にはタレント的に人気が高い選手が多くいます。ボランティアに参加した人限定で選手の生い立ちや日々のトレーニング、生活に関するお話を聞けるイベントを開催し、選手としては自分のことをより多くのファンを獲得する場として、そしてボランティアの方としては他の人が聞くことができないスポーツ選手の考え方やスポーツに対する姿勢について詳しく知ることができる知的欲求をみたす場として提供します。
そうすれば、不特定多数の方に様々なスポーツの魅力が伝わる機会となり、東京都としてもより多くの人にボランティアとして参加するモチベーションを与えてくれるものとして評価してくれるでしょう。
(2)交通費の支給を柔軟にする
一律で交通費が1000円支給となっている場合、例えば10万人に支給するとすればそれだけで10億円の支出となります。そこで、東京都に住んでいる人は半額の500円、遠方の人はその分支給すると言った形で各々の価格を変動させるダイナミックプラシングの仕組みを導入することができればより多くの地域の人がボランティアに立候補してくれるでしょう。
(3)ボランティア大使として有名人を起用する
国内外の有名人をボランティアの代表として招待し、話題性を生み出すことも一つの提案として考えられるでしょう。その人の知名度を活用するだけでなく、ボランティア全体の代表としてその人がいることで一体感を高めることができ、ボランティアチームに所属する魅力を感じてもらうことでボランティアの人数を増やすことができます。
2.【解答例つき】「 個人問題ケース」の練習問題
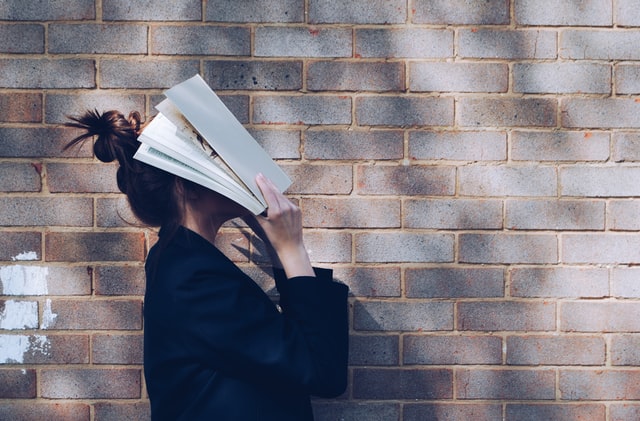
続いて、個人的課題を解決する「個人問題ケース」についてみていきましょう。題材は「単位取得計画をどのように立てるか?」というものになります。
【ストーリー】
あなたの友人は大学4年生で卒業要件である取得単位数まであと30単位です。この大学では年間32単位までしか申請できず、彼女は卒業を確実なものにするために単位取得計画を立てることに決めあなたに相談してきました。彼女は今のところ毎日2時間の学習時間で15科目分(30単位)を取ろうと考えているようです。あなたならどのような単位取得計画を立てますか?あるいはどのような習慣が彼女の単位取得を手助けする上で必要なのでしょうか?7分で考えて説明してください。
A. 前提条件と課題の確認
部活やサークル、バイトなど大学生は意外と忙しいもの。あなたも単位を取り損ねた経験やギリギリで取得できた経験があるのではないでしょうか?今回はあなたの友人が卒業のために単位を確実に取りたいという相談です。これまでの生活では単位取得が危ういということですから、彼女の生活や習慣の改善がこのケース問題におけるボトルネックといえるでしょう。
B.現状の分析
彼女の生活が乱れる、つまり単位取得に必要な学習時間を十分に確保できない原因はどこにあるのでしょうか。
(1)時間的制約
それぞれの科目の1授業につき、内容を理解するために必要な時間数が予習時間(0.5h)+復習時間(1h)+授業時間(1.5h)とすると、一つの科目につき15週間授業があるとすれば前述した式に15(回)を掛けて、総復習の時間を足し合わせれば単位取得に必要な時間数を概算できます。
一科目の単位取得に必要な時間の目安
15×(0.5+1+1.5)+15=60(時間)
各学期4ヶ月間のうち、前期8科目、後期7科目を取得するとして各期で必要な勉強時間数を求めると前期は480時間、後期は420時間必要になります。
単位取得に必要な1日の勉強時間の目安(理想)
前期:480 ÷ 120 = 4 (時間)
後期:420 ÷ 120 = 3.5 (時間)
理想的な状況においては起きている時間(16時間)の25%だけ勉強すれば、単位取得ができることが分かります。
(2)能力的制約
上記のように時間的な制約だけ考えれば毎日3~4時間学習を続ければ単位を取得できますが、現実はそのようにはいきません。なぜなら、毎時間学習効率を100%にするのは不可能だからです。
そのため、ここで学習率という概念を加えて、毎時間80%の内容を学習できるというように仮定します。すると、4時間の学習は3.2時間分の学習ということになるので、本来の時間分学習するには5時間の勉強時間の確保が必要になります。
単位取得に必要な1日の勉強時間の目安(現実)
前期:4 ÷ 0.8 = 5 (時間)
後期:3.5 ÷ 0.8 = 4.4 (時間)
(3)外的制約
(1)と(2)では時間と個人の能力をベースとした定量情報を考えてきました。しかし、大学生は何も勉強だけで生きているわけではありません。サークル活動や飲み会の誘いなど多くの誘惑が伴います。そのような外的な制約が加わった時、彼女は毎日コンスタントに学習時間を確保できるのでしょうか。
C.フレームワークの利用とボトルネックの特定
今回利用するフレームワークは問題を質的な部分と量的な部分に大別するフレームワークです。これを用いることで、両方の側面から効果的なアプローチを展開できます。
具体的に今回の例で問題となっているのは学習時間(量)と学習効率(質)です。これらを掛け合わせたときに必要とされる学習量に達するかどうかが単位取得の鍵となります。そのため、ボトルネックは彼女が勉強を集中して続けられるかどうか(外的な誘惑に負けないかも含む)という点とそもそもの絶対的な学習時間を確保できるかという点になります。
D.対応施策(打ち手)の提案と評価
さてA~Cまでのことを踏まえ、どのような打ち手(施策)が効果的でしょうか?以下に解答例を示しましたので確認してみてください。
(1)朝6時に起きて8時まで勉強するように説得する
日々、大学生は予定が変わりそれに対応するのは難しいものです。しかしながら、卒業ということを目標掲げている以上、全ての元となる学習時間を確保することが必須用件となります。
彼女は現在2時間の学習で単位を取得しようとしていますが、(B)の現状分析をへて、2時間~3時間ほど学習時間が足りないことが分かりました。そのため、毎朝起きる時間を前倒しすることによって現在の生活リズムを崩さずに時間を確保することを提案します。
(2)第三者によるスケジューリングの定期的な見直し
(1)に関連して予定が流動的に変化しやすい状況を加味し、自分に毎週の勉強時間を報告することを提案します。外的なプレッシャーを与えることで絶対的な時間数の向上を期待し、毎週どのような学習計画に沿って勉強をしているかということを自分でも再確認させることで達成感などを感じるようにしましょう。
(3)スタディグループの設立
大学のゼミのように苦手分野について素早く学習を進めることができるように彼女の友人たちとグループを作って勉強することを提案します。この時、単なる友達ではなく授業でたまたま隣に座った人などとあえてグループを作らせることで、余計な時間を過ごさないよう工夫させることも考えます。
覚えておきたいケース面接対策の3つのコツ

上記の例を踏まえて対策のコツを以下にまとめましたのでご確認ください。
①解決する問題のボトルネック(根本)を確認する
ケース問題で想定される状況は企業の利益増大を目指すものや個人的な課題の解決まで幅広いため、単なるアイデア勝負では議論が発散してしまい効果的な提案はできません。そのためクライアントがまずどのような状況に置かれているかを整理し、どこを変えれば最も効果的なインパクトを生み出せるかを最初に想像しなければなりません。
②前提条件を詰めて、土台をしっかりと作る
ボトルネックを特定する際は上記のBで行ったような現状分析が必要不可欠です。どのような団体や人が関わってくるのかといったターゲティングを行うことで最終的な打ち手施策がより効果を発揮します。
③結論は明確に
ケース面接で面接官に伝えなければならないのは短い時間で考えた提案とそれに到達するまでのプロセスです。どちらかが欠けていると評価が低くなりますし、そもそも結論にたどり着くまでのプロセスだけを説明してもそれは本末転倒です。時間を区切って提案とプロセスの両方を説明をすることを心がけましょう。
【実際に解いてみよう】ケース面接の練習問題

以下にケース問題のストーリーを一つ紹介しますので、復習としてぜひ解いてみてください。AIDMAを使っても構いませんし、自分なりにボトルネックを特定し論理的に7分で準備し、5分ほど話せるかを試してみましょう。
【ストーリー】
あなたはある牛丼チェーンから相談を受け、日本国内の牛丼チェーンにおける売り上げを伸ばしたいと相談を受けました。国内の敷地には限界があり、国際市場でもあまりプレゼンスが向上していないことからまずここ数年で国内での収益基盤を固めておきたいという経営方針だそうです。目標は定量的には決まっておらず、出来る限り伸ばしたいということでした。あなたはどのような方法であれば売り上げを伸ばすことを提案しますか?
7分で考えて説明してください。
まとめ

ケース面接では課題そのものの出来だけでなく、立ち振る舞いやコミュニケーション能力も重視されます。プレッシャーがある中でお客様の前で失礼な言動がないか、論理性が崩壊しないかという点については必ずクリアする必要があります。
以下にケース面接基礎対策編のポイントをまとめましたので確認してみてください。
- ✔ ケース面接では解決すべき課題は何かをまず明らかにする
- ✔ ボトムネックを特定し、前提条件を整理し打ち手策のターゲットを絞り込む
- ✔ わかりやすい提案をいくつか立て、面接官と議論を通して提案に深みを出していく
短い時間の中でフレームワークを駆使して考えて発表することは難しいことですから多くの練習が必要です。しかし考え方の枠組みばかり気にしていると肝心の提案が弱くなってしまいますので、クライアントが本当に求めているものは何か考えるということを忘れず面接に臨んでください!
基礎編を読了した人は、応用編もチェックしてみてください!
【徹底解説】ケース面接をわかりやすく解説!基礎的なフレームワークから身につける実践学習 -応用対策編-
RANKING
人気記事ランキングTOPIC
新着記事