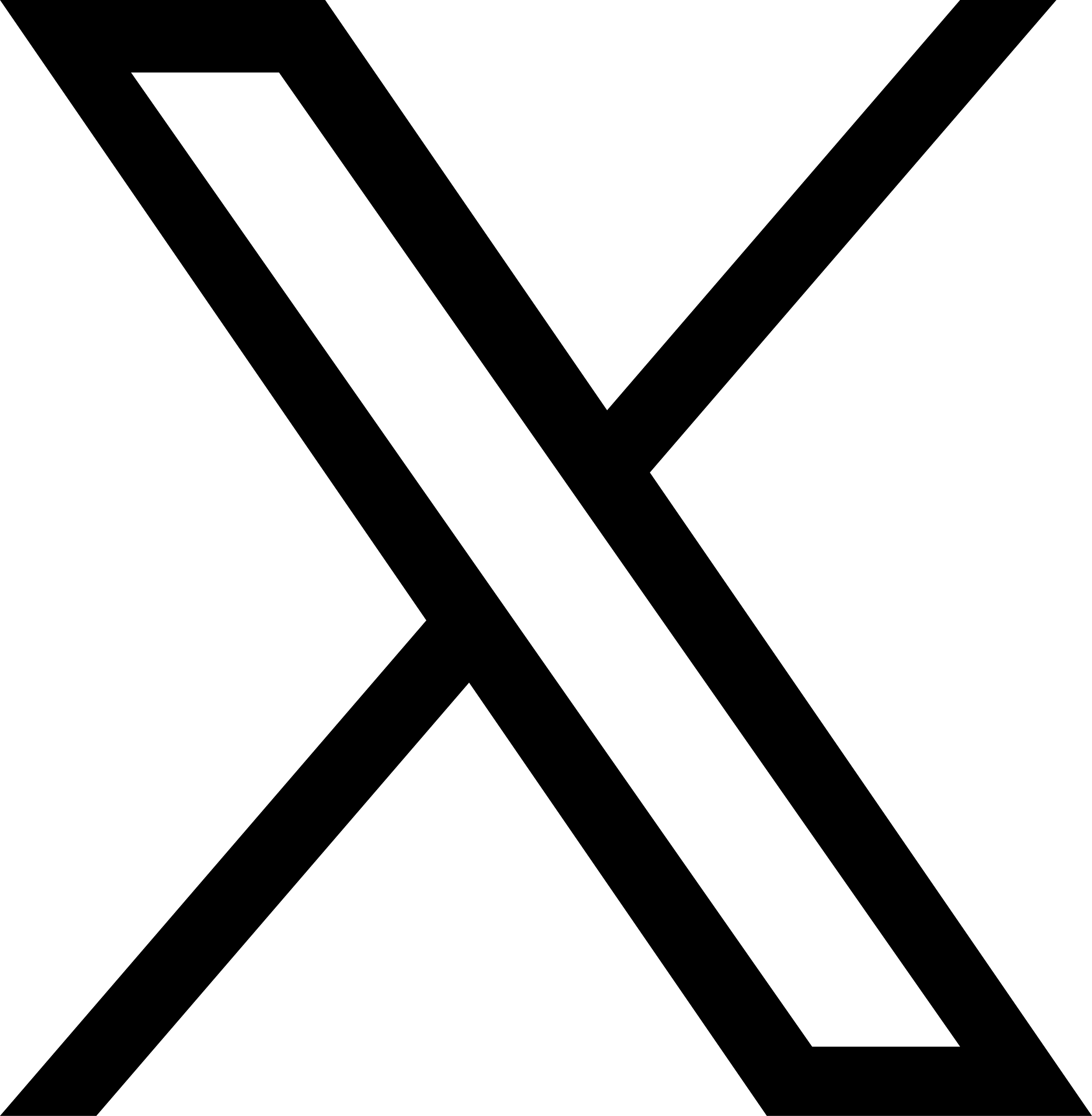【新卒:業界研究】冠婚葬祭業界の特徴|仕事の魅力から今後の動向まで
サービス
CONTENTS

冠婚葬祭業界とは?
どんな業界に区別できる?
冠婚葬祭ビジネスの仕組み
ブライダル(ウェディング)のビジネスモデル
葬儀のビジネスモデル
冠婚葬祭業界の主要企業
ブライダル(ウェディング)業界の主要企業
葬儀業界の主要企業
冠婚葬祭業界で特徴的な職種
ブライダルにおける職種
葬儀における職種
冠婚葬祭業界の現状と課題
ブライダルの回復は未だ兆しがない
葬儀業界は競合の多様化と葬儀の簡素化が進む
まとめ
就職活動に避けて通れない業界研究。今回の記事では結婚式やお葬式など人生の節目に関わり、重要な役割を担う冠婚葬祭業界について詳しく紹介していきます。大手企業の情報はもちろん、職種別の特徴や今後の業界予想などこの記事を読むだけで冠婚葬祭業界の最新動向を把握できます。冠婚葬祭業界に興味のある方はぜひ一読してみてください!
冠婚葬祭業界とは?
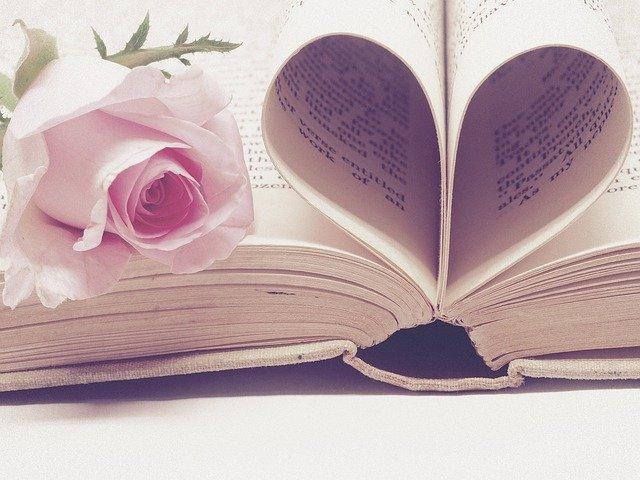
そもそも「冠婚葬祭」とは古来より日本で重要視されてきた「元服」、「婚礼」、「葬式」、「祖先」の祭祀を指します。「元服」とは人生の節目をお祝いする儀式と捉えられており、代表的なもので言えば成人式や七五三などが挙げられます。「婚礼」とはその字面の通りに夫婦や結婚などに関する儀式のことを指し、結婚式や結納などが例として挙げられます。「葬式」は人間の死に関わる儀式のことを指し、「祖先」の祭祀は正月や節分など親族の交流を伴う1年の節目の行事を指します。
その中でも婚礼と葬式は大人数を巻き込んで行われるセレモニーであることから場所や食事の確保、進行の管理などが大変になります。こういった課題から専門業者が発展し、今では顧客体験を重要視したサービスが展開されるようになったということです。
どんな業界に区別できる?
日本の冠婚葬祭業界は主に以下の業界に分類できます。
・ブライダル(ウェディング)業界
結婚に関わる事業を総合的に展開する業界です。結婚式自体の開催に伴う式場の手配から当日の進行等はもちろん、婚活支援を目的とした情報サービスの提供やレストラン・ホテル運営など多岐にわたって事業を展開しているのが特徴です。
・葬儀業界
葬儀や祭事などの企画・執行を全般的に行う業界です。葬儀業界という区切り方であれば墓地に利用する墓石などを扱う石材店なども含む場合もあります。葬祭業者を中心に火葬場や寺院、ギフト業者や食品業者(仕出し等)などが業界を形成しています。
冠婚葬祭ビジネスの仕組み
冠婚葬祭は日常的に関わりがない業界である分、どのようにビジネスが展開されているのかわからない方も多いと思います。ここでは簡単にブライダルと葬儀がどういう仕組みでサービスを提供しているのかを説明します。
ブライダル(ウェディング)のビジネスモデル
近年では挙式事業そのものだけでなく、ホテルやメディアなど様々な事業を多角的に展開するビジネスモデルを取っている企業がほとんどです。
挙式をする場所についてホテルや海外マーケットなどと連携して競合他社よりも魅力的なロケーションを提供したり、前撮りを行うスタジオや最新のウェディング情報なども合わせて提供することで、結婚体験の付加価値を高めています。そうすることで収益効率を向上させ、婚姻数や契約数だけに頼らないビジネスを展開できるのです。
葬儀のビジネスモデル
葬儀のビジネスモデルもブライダルのビジネスモデル同様に多角化の一途を辿っています。近年では死亡者数は増えているものの葬儀の簡素化もあり市場規模は横ばいとなっています。しかしながら、葬祭業者を中心となって生花業者や寺院などの各専門業者が連携することで安定的な価値を提供し続けていることから、今後数年で業界全体が急速に縮小することはないと考えられます。
内閣府資料(※1)によると、 2040年においては約170万人の死亡者数が予想されていることから年間約1兆5000億円以上の規模となります。
(※1)内閣府 消費者契約法専門調査会(平成29年)「葬儀業界の現状」
冠婚葬祭業界の主要企業

つづいて冠婚葬祭を支えている主な企業について紹介します。ここを足がかかりに個別の企業研究を進めてみると細かな企業の特色を知ることができるでしょう。ここでもブライダルと葬儀それぞれの分野にわけてみていきます。
ブライダル(ウェディング)業界の主要企業
テイクアンドギヴ・ニーズ
国内最大手のブライダル企業で、2020年3月期の売上高は約636億円です。国内のブライダル事業を主力事業としつつ、海外リゾート・ウエディング事業やホテル事業などへの投資を行い、多角的な経営を推進しています。
同期の純利益は約10億円で近年安定的に黒字を続けています。従業員数も2341人と多く、純資産額も約230億円で安定しています。今後、少子高齢化が進む中でも積極的な成長投資がこの企業の支えとなるでしょう。
参考:「TAKE and GIVE NEEDS 採用サイト」https://recruit.tgn.co.jp/
ツカダ・グローバルHD
ツカダ・グローバルHDは東京都渋谷区に本社を構える大手ブライダル企業です。事業は主にブライダル、ホテル、レストランの3本柱で成り立っています。ゲストハウスウェディングなども特徴的で国内外に様々な施設を活用した様々なプランをクライアントに提供しています。
業績も堅調に右肩上がりで、2019年12月時点の売上高は約600億円、純利益は約25億円です。従業員数も増え続けており、今後も業績の伸びが期待できます。
参考:「採用情報|ツカダ・グローバルホールディングス」https://www.tsukada-global.holdings/recruit/
ワタベウェディング
国内外ウェディング及びリゾート地での挙式を主軸としたブライダル事業の展開が特徴的な日本の大手ブライダル企業です。WATABEグループとしての事業の多様性が特徴的で国内96拠点・海外41拠点のネットワークを生かし、クライアントにサービスを提供しています。特にリゾートウェディングは国内で取扱組数No.1の実績を誇っています。
2019年度の売上高は約約390億円で、純利益は約7億円で順調に業績を伸ばしています。
参考:「採用情報/WATABE WEDDING」https://recruit.watabe-wedding.co.jp/
葬儀業界の主要企業
燦ホールディングス株式会社
燦ホールディングス株式会社は売上高が葬儀業界トップ帯の最大手です。葬儀の簡素化などにより市場規模が横ばいとなっている中で、業績を維持しており2019年度の売上高は約210億円、純利益は約18億円となっています。
2040年までの死亡者数増加を背景とした人々の価値観の変化による葬儀施行単価の下落を予想しつつも、当該グループは競争優位性を「人財」に見出し、採用や人事評価の改革によるガバナンスとサービスの質の向上を目指しているようです。
参考:「燦ホールディングス株式会社」https://www.san-hd.co.jp/
ティア株式会社
ティア株式会社は愛知県名古屋市に本社があり、主に葬儀会館ティアを中心に事業を展開しています。売上高は約120億円となっており、堅調に事業を展開しています。
年間約16,000件の葬儀を執り行っており、明朗な価格設定など消費者にとって親切なプラン設定などが事業を安定させていると考えられます。また、コンビニエンスストアの店舗制度でも用いられるフランチャイズの仕組みなどが導入されていることで独自のネットワークを広げています。
参考:「ティア株式会社」https://www.tear.co.jp/company/
こころネット株式会社
2005年に冠婚葬祭事業のアイトゥアイ・グループと石材などを扱うカンノ・グループとプが経営統合したことで設立された企業です。売上高は2020年3月において約104億円となっています。
元々二つの事業母体が統合してできたこともあり、葬儀自体のビジネスだけでなく、葬儀で利用する商品の販売等についても活発に行っています。他にも再生エネルギー事業や介護事業など、葬儀事業とは別の事業も積極的に展開していることから、葬儀市場が伸び悩む中で事業リスクを分散していると推測されます。
参考:「こころネット株式会社」http://cocolonet.jp/
冠婚葬祭業界で特徴的な職種

結婚式やお葬式では顧客を主役としつつ、多くの職種が運営に携わっています。その中でも特徴的なものを例に説明していきます。
ブライダルにおける職種
・ウェディングプランナー
結婚式の挙式からその事前相談、当日の進行をサポートする職種です。カップルが式場を検討する際に会場の案内や説明を行い、各式場の特徴や予算をもとに理想的な結婚式を共に考え当日まで総合的にサポートすることが仕事です。ウェディングや披露宴に関する様々な知識を生かして、結婚式に関わるドレスコーディネーターや会場とも連携しクライアントの理想の結婚式を実現します。
・ドレスコーディネーター
ドレスコーディネーターはその名の通りウェディングドレスの専門家として花嫁のドレスを提案します。最近では多種多様なデザインや色のドレスがあり、その中から花嫁に最適なドレスを提案するにはトレンドやドレス自体の特徴を正確に把握する必要があります。ドレスコーディネーターはそれらの観点を全て考慮しつつ、花嫁が一番輝けるドレスを提案することが仕事になります。
・ブライダルアテンダー
介添人とも呼ばれるこの職種は当日花嫁や花婿のサポート(アテンド)を行う仕事です。当日は当人たちが緊張している場合もあるので緊張を和らげるお手伝いをしたり、進行状況を踏まえたご案内や花嫁の移動の手伝いなど様々なことを行います。
葬儀における職種
・葬儀ディレクター(メモリアルディレクター、葬祭ディレクター)
遺族の意向をもとに、葬儀の企画や会場の手配・設営、当日の運営や進行を行う職種です。厚生労働省は平成8年3月より葬祭ディレクター技能審査を認可しており、葬祭ディレクター技能審査協会認定試験の実施と葬祭ディレクター認定を行っています。葬儀業を行う際に必ず必要という資格ではありませんが、この試験によって葬祭業における一定の技能水準が確保されているため、認定試験に合格している人も少なくありません。
・納棺師
納棺師はご遺体を棺に納める際に必要な措置や手続きを行う職種を指します。遺族の方と故人の方が顔合わせできるよう腐敗の進行を調整したり、化粧などを行う。葬儀を通して故人との最後の対面に関わる重要な仕事になります。
・エンバーマー(医療従事者)
エンバーマーとは遺体の長期保存を行う措置(消毒等などのエンバーミング)を専門的に行う職種です。日本においてはエンバーミングは遺体衛生保存と呼ばれ、医療行為が許可されている医療従事者や日本遺体衛生保全協会のエンバーマーライセンスを持つ有資格者によって行われます。
冠婚葬祭業界の現状と課題

冠婚葬祭業界を見始めた人に知っておいてほしい現状と課題についてまとめました。大きな特徴としてブライダル、葬儀両方に対する社会の意識変化が密接にかかわっているということです。日本における少子高齢化や所得の減少といった問題は婚姻率の低下や葬儀の簡素化といった事態に結びつきます。
それぞれの課題について詳しく見ていきましょう。
ブライダルの回復は未だ兆しがない
厚生労働省の「人口動態調査(※2)」によれば、近年婚姻数は減少傾向にあり、令和元年における婚姻数は58万3000組と推計されています。このような現状は日本の少子高齢化や初婚年齢の上昇が関係しているとされており、ブライダル業界としては芳しくない状況と言えるでしょう。
また、「なし婚」と呼ばれる披露宴を開催せずに婚姻届を提出するだけの結婚形態や事実婚など人間関係における自由度の向上などもブライダル産業に負の影響を与えていると考えられます。そのため、このまま少子化などが続けばブライダル業界の業績は右肩下がりになると予想されます。
(※2)厚生省「人口動態調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html
葬儀業界は競合の多様化と葬儀の簡素化が進む
死亡件数についてはブライダル業界とは逆に増加傾向にあるものの、思うように各社の業績は伸びてきていません。その背景には儀礼慣習の希薄化、つまり葬儀の簡素化や葬儀事態をとり行う社会的慣習の薄れがあると考えられます。
元々日本では一般的に仏式という形態が取られており、ご臨終後に枕飾りや納棺を経て通夜、告別式と順に執り行われるのが一連の流れでした。しかしながら、最近では葬儀を省いて火葬場に直行する直葬と呼ばれるものも相対的に増えてきていたり、葬儀資金や葬儀自体に対する考えが変化してきていたりすることから、死亡数と市場規模の変化に乖離をもたらしていると推測されます。
まとめ

冠婚葬祭業界は社会通念の変化、結婚や葬儀に対する価値観の変遷によって左右される業界です。 結婚式や葬儀などが簡素化される傾向にあることから業界全体の変革が求められています。 今回の記事では冠婚葬祭業界の特徴と代表的な企業の動向と将来性について詳しく解説しました。 以下に記事のポイントをまとめましたので、確認して理解を深めてください。
・冠婚葬祭業界は全体として市場規模が横ばいである
・高齢化社会の恩恵は限定的でそれぞれの企業が事業の多角化を迫られている。
・社会通念や価値観の変容による影響を受けやすい業界である。
冠婚葬祭業界では人のライフステージの節目に深く携わることができます。 人の幸せや別れを素晴らしいものにしたいという情熱がある方などはぜひさらに深く研究してみてください。 以下の記事では業界研究のさらに詳しい方法についてまとめていますので、ぜひご覧ください!
【テンプレートつき】就活のあらゆる場面で役立つ業界研究のやり方・まとめ方
自分で志望する業界を選ぼう!納得できる業界を見つけて絞るコツとは?
RANKING
人気記事ランキングTOPIC
新着記事