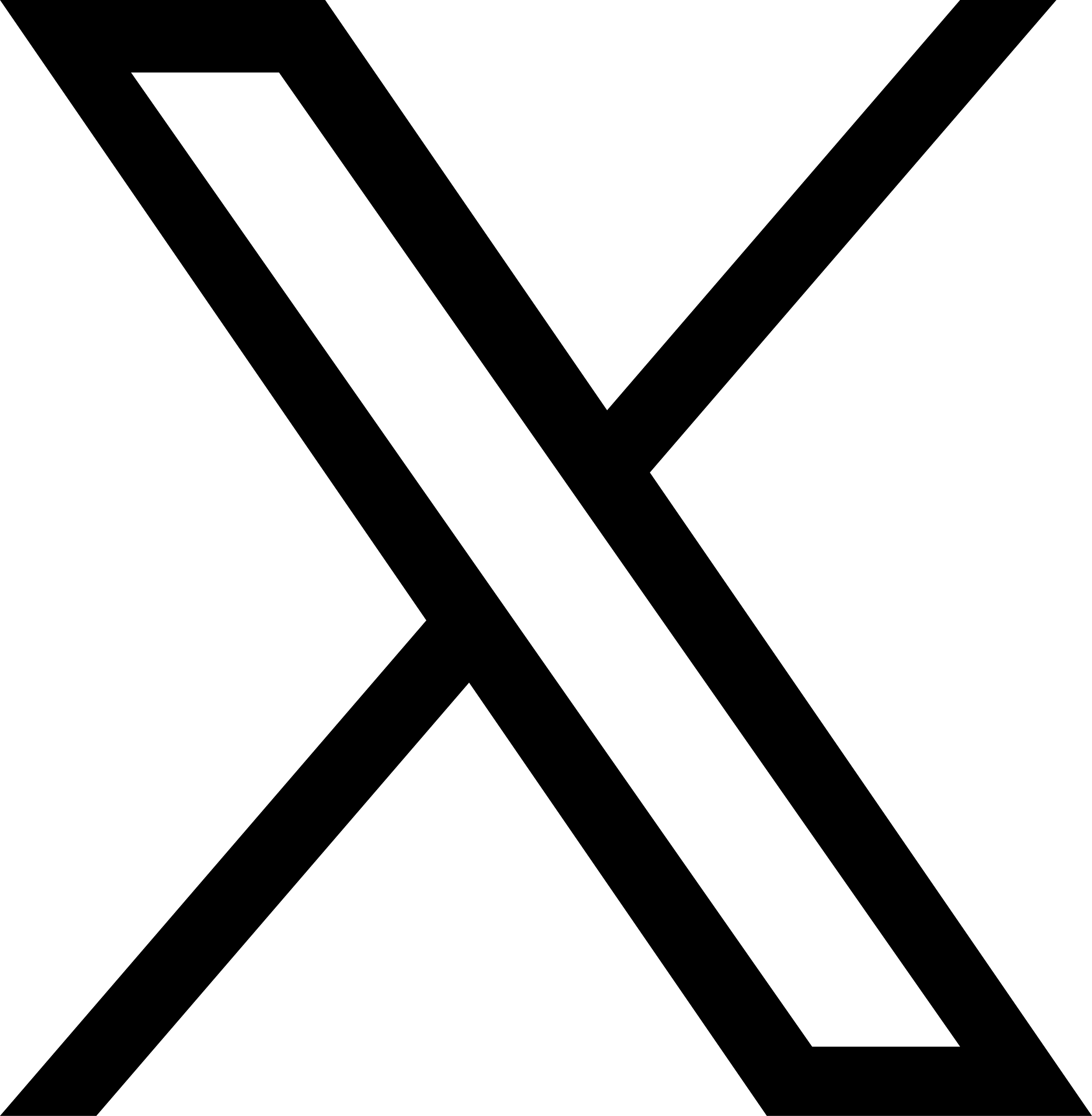グループディスカッションで話せない4つの原因と対策、注意点を解説
グループディスカッション
CONTENTS

企業がグループディスカッションを実施する目的
グループディスカッションで話せない4つの原因と対策
①周りの目を気にしてしまう
②議論についていけない
③自分の意見に自信が持てない
④そもそも自分の意見がない
グループディスカッションにおける注意点
他の人の意見を否定しない
面接官への過度なアピールは避ける
発言していないときの振る舞いも気を抜かない
まとめ
グループディスカッション(GD)といえば、ES/ウェブテストにつづく選考対策の関門です。
就活で経験する機会が多いグループディスカッションですが、苦手な人が多いのも事実です。苦手意識を持つ就活生が多い理由として、グループディスカッションは面接と少し違った見方をされるため、コツを掴まないと短時間で十分なアピールをすることができないからです。
今回は「頑張っても受からない」「なぜ落ちたのかわからない」とお悩みの方の中でも特に、「話すのが苦手」という方に向けてグループディスカッションを克服するコツをお伝えします。
関連ページ:【選考対策】グループディスカッション完全攻略~すぐ実践できる5つのポイント~
企業がグループディスカッションを実施する目的
グループディスカッションには以下3つのメリットがあります。
- 短時間で多くの学生を見ることができる
- 入社後の人間関係をある程度予測できる
- グループディスカッションは就活生同士で行うため、人事は学生を見ることに集中できる。
上記メリットが見込まれるため、企業はグループディスカッションを行っています。場合によっては、就職説明会の後にそのままグループディスカッション選考が行われることもあります。
また、グループディスカッションは就活生の人柄が見えやすいという点でも有効です。選考では、就活生が他の就活生とグループワークをする際にどのような行動をとるかを見ています。1対1の面接では把握しきれない就活生の一面を垣間見ることができるのです。
グループディスカッションで話せない4つの原因と対策

グループディスカッションで上手く話すことができず苦手意識を持っている方も多いと思います。上手く話すことができない原因として、以下の内容が考えられます。
- 周りの目を気にしてしまう
- 議論についていけない
- 自分の意見に自信がない
- 自分の意見がない
下記ではこれらの原因と対策に関して詳しく見ていきたいと思います。
①周りの目を気にしてしまう
面接官や同じチームのメンバーの視線を過度に気にしてしまい、自分の意見を発言できなくなっている状態です。自分に向けられる周囲の目を「気にしない」というのは難しいため、まずは何のためにこの面接に参加して、最終目的は一体何なのかを再確認することが重要です。改善策として、まずは思考を「目的思考」に変えることが大切です。
②議論についていけない
議論についていけないからといって、理解しないまま進めてしまうのは危険です。たとえば同じチーム内のメンバー同士連携を図り「ここまでの話の流れやポイントをまとめさせてください」などの声かけが重要です。このような声がけを行うことによって、チーム全体の認識を統一させたいといった体で内容の再確認を行えます。
③自分の意見に自信が持てない
グループディスカッションの多くは絶対的な正解がないテーマが与えられるので、自分の意見が正しいかどうかを気にする必要はありません。それよりも、自分の意見を表現することが重要です。
あなたが意見を述べないことには、面接官も評価材料がなく評価のしようがありません。反対されるのが怖い場合は「私は○○と思いますが、皆さんいかがでしょうか」と言うようにあくまで意見のひとつにしか過ぎないことを前提に、皆さんの意見も聞きたいと言った体で進めると良いでしょう。
④そもそも自分の意見がない
なかなか自分の意見が浮かばない場合、周囲の人の意見を聞いてその意見をまとめるとともに、自分自身の理解を深めていくことが大切です。
その中で「この意見は良い」「自分の考えに近い」と思うものがあれば「なぜその結論に至ったのか」「なぜその意見に賛同できたのか」などを話すことで、1から自分の考えを出すことなく意見を出すことができます。
グループディスカッションにおける注意点

グループディスカッションにおける主な注意点としては下記が挙げられます。
- 他人の意見を否定しない
- 面接官への過度なアピールは控える
- 発言していない時の振る舞いも気を付ける
各々の注意点を解説していきます。
他の人の意見を否定しない
グループディスカッションでは、たとえ自分と異なる意見があった場合でも否定せず、1度その意見を受け入れた上で提案しましょう。
他の人からの意見を真っ向から否定してしまうと相手が威圧感を感じてしまい、周囲の雰囲気が悪くなる可能性があります。
グループでひとつのテーマについての結論を出さなければならないグループディスカッションでは、1人の意見のみを取り入れるのではなくグループ全体の意見を取り入れる必要があります。
誰しも自分と全く同じ考えを持っている人はなかなかいないため、自分と異なる意見が出てくるのは当然です。自分と異なる意見が出たからと言ってそれを否定するのは得策とはいえません。
まずは1度相手の意見を受け入れて、その上で相手に自分の意見を伝えながら結論を出していきましょう。
面接官への過度なアピールは避ける
面接官を意識しすぎると、面接官へのアピールに力が入りすぎてしまい独りよがりのパフォーマンスが目立ってしまいます。その結果、面接官からは協調性がないと判断される可能性があります。
最大の目的はチームで協力しながら議論を行い結論を出すことです。その目的を念頭に置いて行動すれば、過度に緊張せずに自然体で臨むことができ、結果的に良いパフォーマンスを発揮できるでしょう。
発言していないときの振る舞いも気を抜かない
グループディスカッションでは、何よりもまず発言することが大切です。しかし発言だけに集中してしまい、発言をしていない時に気を抜いてしまうのは危険です。
他の人が話している時は、相手の目を見て注意深く聞き、話す機会を与えることも大切です。自分が話していないときの行動も評価の対象になるので注意しましょう。
まとめ

話すことが苦手な人にとって、グループディスカッションは難易度が高く感じられるでしょう。しかし、コツを掴みポイントを押さえることで乗り切れる可能性があります。
- 自分の意見を発言することが難しければ、他の人の意見をまとめ補強することでチームに貢献する
- 他の人の意見を否定せず、発言していないときの振る舞いも気を抜かない
グループディスカッションを克服する第一歩として、まずは上記の点を心がけましょう。
就活をスタートしたばかりの時期はなかなかグループディスカッションのコツを掴めなかったり、ポイントを押さえられなかったりしても、回数をこなしていくことで少しずつ悩みは解消されていきます。
しかしそれだけでは不安ということであれば、グループディスカッションを開催している企業へのエントリーを増やしたり、就活エージェントでグループディスカッションの練習をしたりすることで、練習する機会を得られます。
私たちJobSpringの面談では、ひとりひとりの話を聞き寄り添うことでグループディスカッションでの振る舞いなどをアドバイスしています。また、グループディスカッションに落ち続けてしまい悩んでいる方には、原因を探るためのフィードバックも行います。
さらにグループディスカッションの選考を行っていない企業を紹介することも可能なため、自分にピッタリの選択肢を見つけることができます。
実際に会って話すからこそ、皆さんの性格に合ったサポートを心掛けているので、ぜひ一度JobSpringの面談にいらしてください!一緒に皆さんにぴったりの会社を見つけましょう。
RANKING
人気記事ランキングTOPIC
新着記事