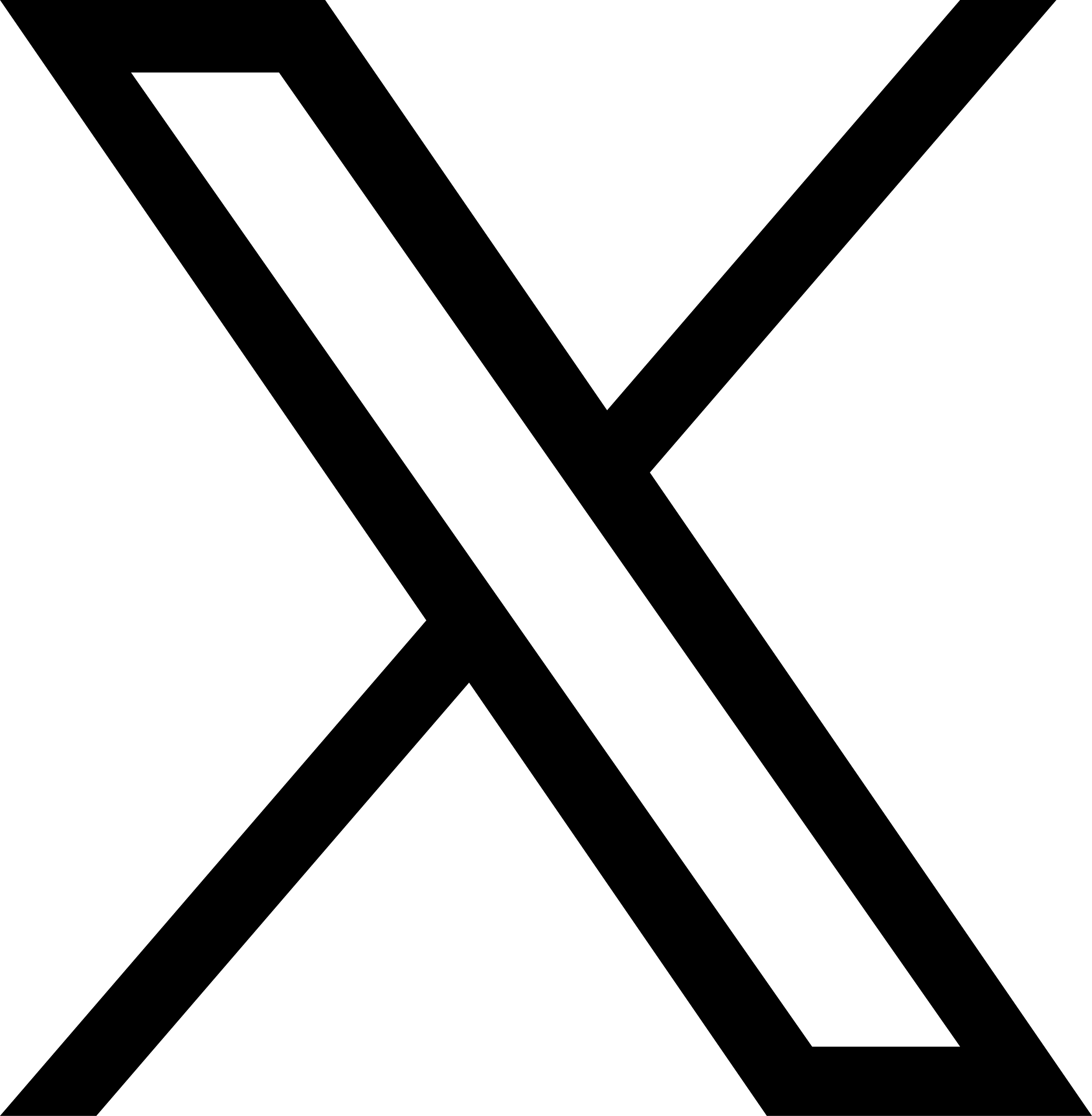よく聞く「フェルミ推定」ってなに?考え方のコツから練習方法まで一挙解説
用語
CONTENTS

フェルミ推定とは?
どのような時に使われる?
出題される傾向が高い業界
フェルミ推定はもう古い!?
そもそも何を見ているのか
今後の面接からは消える?
フェルミ推定でおさえておきたい考え方
①重視すべきは正しさよりも論理性
②前提条件や仮定は最初にもってくる
③手がかりになる数字はあらかじめ知っておく
④求めたい値を常に意識する
フェルミ推定力を身に着ける練習方法
①日常を切り取って問題提起する
②紙に書いて論理の流れを観察する
まとめ
「アメリカのシカゴにいるピアノの調律師は何人か」突拍子な質問とともに繰り広げられる面接。一時グーグルの採用方法として取り上げられ、効果の有無が話題となった「フェルミ推定」について、使用される業界、目的、考え方から練習方法まで、1から説明していきます。
フェルミ推定とは?
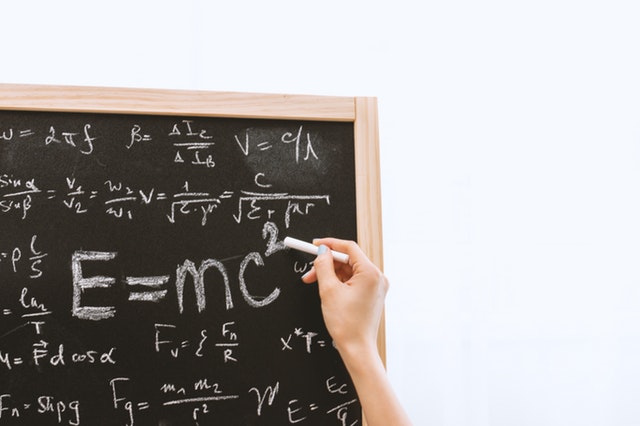
どのような時に使われる?
実際に調べることができない数量を、ある程度の予備知識をもとに論理的に短時間で概算する方法をフェルミ推定といいます。
導入の質問文の正しい数量を回答者(就活生)が事前に知っていることはほぼないでしょう。質問文の例題はフェルミ推定の産みの親、フェルミさん自身がシカゴ大学の生徒にだしたとされる問題です。この問題に関して必要とされる「ある程度の予備知識」をアメリカ人の視点から考えると
<シカゴの人口は約300万人であること>
この一点しか予備知識として期待されていないでしょう。これから先の概算については、回答者の仮定の論理に漏れがないかが重要性になってきます。
出題される傾向が高い業界
コンサルティングファーム、外資系企業で多く出題される傾向にあります。新規プロジェクトを立ち上げる際により具体性を伴った提言ができる、論理的に説明することができるかどうかといった思考力を問う課題として出題されます。
フェルミ推定はもう古い!?

そもそも何を見ているのか
- ・問題解決のセンス…未知の課題に対してどのような視点で切り込むのか、どのように解決の糸口を探すのか
- ・論理の整合性…仮定は妥当であるか、仮定に漏れ・重複はないか
- ・提案力…問題設定から、論理の整合性の説明までの全行程を質問者を納得させる形で行えるか
フェルミ推定を必要とする課題は、企業活動の原則「問題設定→解決策の準備→営業」の一連の流れを不足なく行えるかをチェックしているのです。
今後の面接からは消える?
フェルミ推定を用いた採用活動の効用を疑問視する声があります。グーグルがフェルミ推定の質問を用いて採用した人材の業務能力を研究したところ、質問に回答できたことと、将来的に業務で発揮できる能力とは相関がないことが明らかになりました。自社の採用方法自体がグーグルの研究対象になっており、グーグルのビックデータを元に棄却されたという事実から、フェルミ推定を用いた試験の有効性が疑問視され、その影響力を失いつつあります。
フェルミ推定でおさえておきたい考え方

①重視すべきは正しさよりも論理性
面接官が見ているポイントは概算の結果の正確さではありません。正解のない未知の問題に対して回答者がどのような論理的アプローチをしていくのかを見ています。データが与えられていない環境でどのように問題を定義し合理的に解決していくのか、その過程を面接官に示しましょう。
②前提条件や仮定は最初にもってくる
論理的な説明をする際に回答者が問題をどのように定義するか、前提条件として利用するデータ、仮定は最初に網羅して説明しましょう。「日本人が年間で消費するパンの量は何万斤か」という例をもとに説明すると
【前提条件】
- ・日本の人口1.2億人
- ・雇用者数5300万人
- ・高齢化率(65歳以上の総人口における割合)25%
【仮定】
- ・一般的なパン派:ご飯派の比率を4:6とする
- ・雇用されている人は忙しいため朝の食事としてパンを好むのではないか
→雇用者数におけるパン派、ご飯派の比率を5:5に補正する
- ・高齢者はよりご飯を好むのではないか?
→高齢者には2:8で補正する
- ・朝ご飯としてパンを食べる人はパンを1日1.5切れ消費するとする。
- ・関西の人は5切れで一斤に対して関東は7切れで一斤を消費するとする。
→関西、関東の人数比を4:6とすると、全国平均の一斤の枚数は
(4×5+6×7)/10=6.2(枚)
≒6枚であるとする。
前提条件、仮定が揃ったので①労働者、②高齢者、③その他の3ケースの食パン消費枚数を計算する。
- ①5300(万人)×5/10×1.5×365
- ②12000(万人)×1/4×2/10×1.5×365
- ③(12000-5300-3000)×4/10×1.5×365
計算式を整理して
- (5300×5+3000×2+3700×4)×1/10×1.5×365
- =(26500+6000+14800)×1/10×1.5×365
- ≒4730×548
- ≒2592040(万枚)
2592040万枚の食パンが1年に消費されていることが概算されました。
③手がかりになる数字はあらかじめ知っておく
前提条件として使うデータが多いほど概算の論理性は保障されやすいです。覚えておくデータとしては
- ・総人口系
- ・物価系
- ・国土面積
- ・寿命系
- ・世帯数
などがあります。
④求めたい値を常に意識する
最終的に求めるべき値を概算することを忘れてはいけません。例題として問われていることは「日本人が年間で消費するパンの枚数は何万枚か」ではなく「何万斤か」という点が重要です。枚数を1斤あたりの枚数で割る過程を忘れずに行いましょう。
2592040/6=43200(万斤)
また質問で「何斤か」と問われたからこそ関西・関東圏での食文化の違いにフォーカスすることができたので、常に求めたいデータを意識することが重要です。
フェルミ推定力を身に着ける練習方法

①日常を切り取って問題提起する
例題として取り上げたパンの枚数についてのフェルミ推定は、著者が見たアニメ内の話題として取り上げられたものでした。「日本人が米を一粒残して毎日捨てたとしたら、年間で何キロのお米が無駄になるのか」といった子どもながらの素朴な疑問などを実際に取り上げて、日常からフェルミ推定を結びつける習慣ができると良いです。
②紙に書いて論理の流れを観察する
実際の面接の際、計算はメモ上で行うことができますが、説明は口頭です。5分といった短い時間で論理的に回答するには、自身の論理の流れをとめどなく示せなければなりません。このとき練習の時点から口頭で行うと、自身の論理の漏れなどを確認することが難しいです。ミスの発見、ロジックの再確認のためにも紙面上で問題を解くことを勧めます。
まとめ

未知の数量を仮定をもとに概算するフェルミ推定の、方法、ロジックの展開について説明してきました。その効用自体が疑問視されている現状がありますが、多角的に事象を把握する力など、他の面接において必要とされる論理的な思考の訓練のひとつとしては優秀です。頭の別の使い方のお供に練習してみるのはいかがでしょうか。
RANKING
人気記事ランキングTOPIC
新着記事