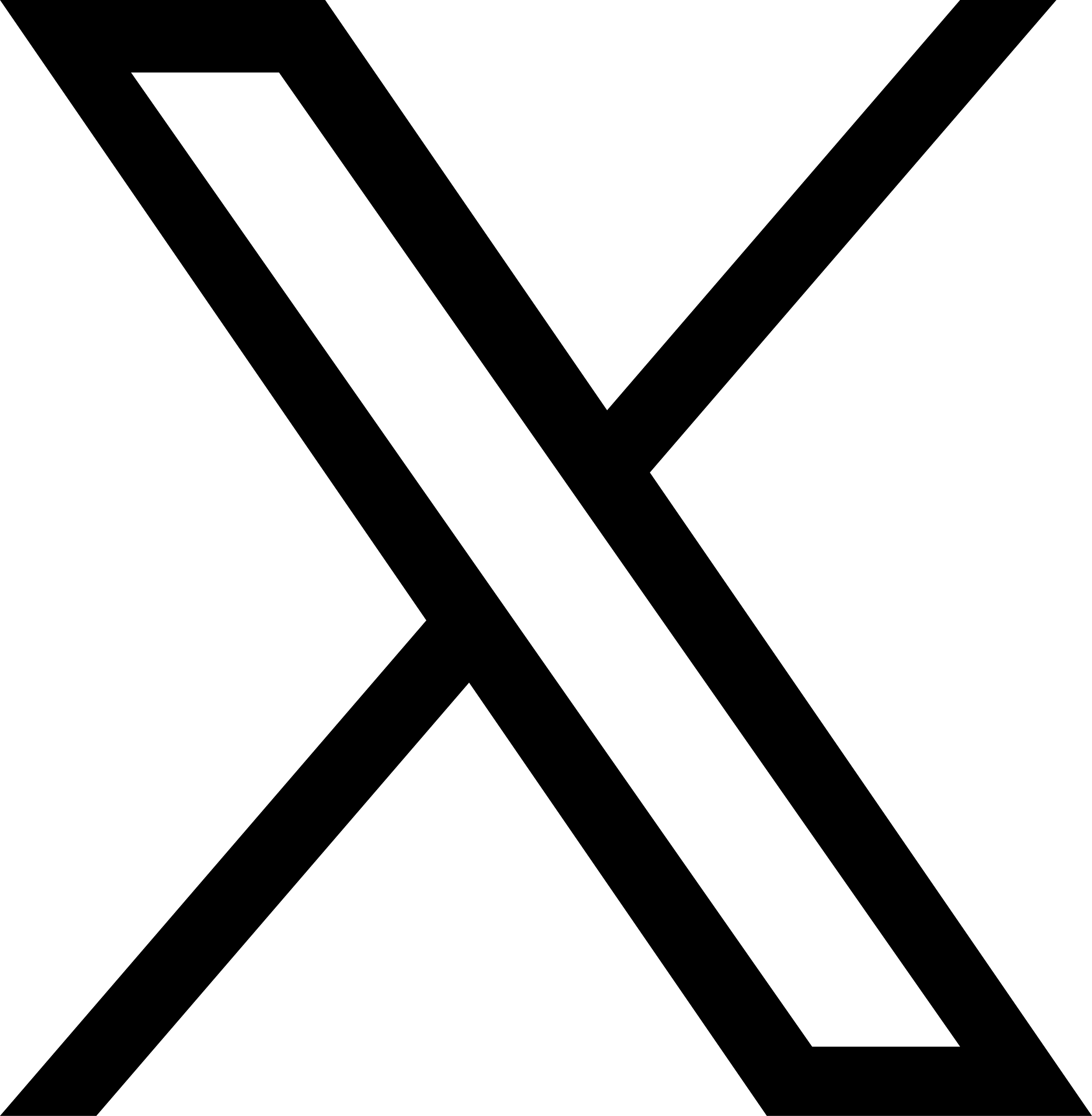就職先の決め手は?決め方と決める際の注意点もあわせて解説
研究ノウハウ
複数内定をもらい、結局どの就職先にしようか迷っている人は多いと思います。
そこで今回の記事では、複数内定をもらった時の就職先の決め方や注意点などに関して見ていきたいと思います。
今回の記事を最後まで読んで頂くと、自分に合った就職先の決め方ができます。
就職先の決め手となる主な要素

複数内定をもらった場合、どこの会社に就職しようか迷ってしまうと思います。
就職先の決め手となる要素として、たとえば自分がやりたい仕事ができるかや実際に働いている社員に魅力を感じ自分も同じようになりたいと思えるかなどが決め手になると思います。
今回は就職先の決め手となりえる要素を以下に6つ挙げました。
- 仕事内容
- 労働環境
- 社風・人間関係
- 年収
- 福利厚生
- 勤務地
詳しく解説していきます。
仕事内容
同じ職種であっても、会社によってできる仕事やできない仕事の範囲が異なります。複数内定をもっている場合、その会社での主な仕事内容はどんなものか、一方でできない仕事内容は何なのかをしっかり確認することが重要です。
労働環境
ある会社は労働時間が残業も含め1日8時間を超えますが、一方の会社ではほとんど残業がなく定時で仕事を終えることができます。おそらく多くの就活生が後者の会社へ入社を決めるのではないでしょうか。
さらに自身の成長を実感でき、キャリアアップを望める環境がある会社に多くの人が入社したいと思います。
このように労働環境と一口にいっても労働時間や環境的要因などさまざまな要因が重なるため、なかなか判断が難しいところではありますが、隅々まで会社のことをリサーチすることが大切です。
社風・人間関係
入社を決める際、社風や人間関係を重視している人は多いでしょう。社風が自分の考え方と近いか、この先自身が社風に沿って仕事をしていけるか否かで判断すると思います。
さらに人間関係においては、社内の人間関係のみならず実際に働いている社員がいきいきと働いているか、自分も同じようになりたいと思えるような魅力を社員に感じるかどうかが重要です。
入社前にはどんな人と働くのか分からない部分が多いため、企業研究の段階で社風や従業員の雰囲気に着目しましょう。
年収
年収も就職先を選定するうえで重要な要素となります。充実した生活を送るにはある程度の年収が必要となるため、収入の確保は重要であることを頭に入れておきましょう。
しかし、年収にばかり囚われてしまうとやりたい仕事ではない会社へ就職してしまうなど、入社後のミスマッチが起こる可能性も否めないため注意が必要です。
福利厚生
一般的に福利厚生や手当などが充実している会社は、働きやすい会社として定評があります。複数内定をもらっている場合、どこの会社が最も福利厚生が充実しているか否かで判断することも重要です。
たとえばライフスタイルの変化などで一時的にキャリアを中断せざるをえない状況になっても、働き続けることができるか否かなどに着目して見ていくのも有効です。
勤務地
会社によっては転勤があり、慣れ親しんだ土地で長く働くことが難しい場合があります。そのため、転勤が問題ないのか否かも就職先を決める大きな要因となりえます。
複数の内定先から就職先を決める際のポイント

複数の内定先から就職先を決めるポイントを知りたい方も多いと思います。ここでは以下3つのポイントを挙げて解説していきたいと思います。
- 就活の軸を再確認する
- 軸に一番マッチしている企業を選ぶ
- 一つの軸で選べない場合は次点で優先している項目で比較・検討
就活の軸を再確認する
就職先の会社に求める条件や何を大切していきたいかなど、就活の軸をもとに就活を進めていた方は多いと思います。しかし、内定が決まった企業が多くなるにつれて、自分が定めた軸のことを忘れてしまう場合があります。
軸を忘れてしまうと就職先に求めることがブレてしまい、入社後にミスマッチが起こる可能性があるため、複数内定をもらっている時ほど就活の軸を大切にする必要があります。
軸に一番マッチしている企業を選ぶ
複数内定をもらった場合、自分自身が就活を行う最初に決めた軸にどの程度マッチしているか否かで就職先を決めると入社後のミスマッチは起こりづらいです。そのため複数内定をもらった場合の就職先選定時のポイントとなります。
一つの軸で選べない場合は次点で優先している項目で比較・検討
自身の就活軸で複数の企業が競合している場合など、ひとつの軸では選べない場合もあると思います。
この場合、冒頭で紹介した決め手に優先順位をつけ、上から順番に比較・検討する作業を繰り返すとおのずと自分に合った就職先を選定できます。
就職先を決める際の注意点
就職先を決める際の注意点は以下3つが挙げられます。
- 第三者の意見は参考程度にとどめる
- ネームバリューだけで決めない
- イメージや思い込みを排除して比較する
詳しく見ていきましょう。
第三者の意見は参考程度にとどめる
第三者の意見は自分にない視点から物事をとらえている場合があるので、参考にするのはもちろん良いことです。
しかし、最終的な判断軸として第三者の意見を鵜呑みにするのはおすすめできません。なぜならその会社で働くのはほかでもない自分自身だからです。
そのため自分の価値観で決めることが大前提です。人の意見で就職先を決めて失敗した場合誰も責任が取れず、後悔する可能性があるため注意が必要です
ネームバリューだけで決めない
ネームバリューがある会社は漠然と有名だから大丈夫と思ったり、仕事内容に魅力は感じないがネームバリューがあるから何とかなると思ったりする方は多いです。
しかし、重要なのはネームバリューではなく自分自身にその会社があっているか否かなので、ネームバリューだけで会社を決めてしまうのは危険です。
イメージや思い込みを排除して比較する
とくに大手企業などは世間一般的に安泰や優良企業などさまざまなイメージを持たれているケースが多いです。
しかし実際に入社してみるとイメージとかけ離れていたなど、自分自身のイメージや思い込みのまま就職先を決めてしまうと後で後悔することになるケースもあります。
イメージや思い込みを排除し、客観的に会社を見ることが重要です。
面接で「就職先の決め手はなんですか?」と聞かれた際の回答例

実際の面接で就職先の決め手はなにかと質問された場合の例文と解説を下記で見ていきましょう。
回答例
「就職先の決め手は、責任ある仕事を早くから任せてもらえる環境であるかどうかです。多くの会社では新人の頃に任せてもらえる仕事の幅は少ないと思います。
しかし、早い段階から責任ある仕事を任せてもらえるとなると、自分を信用してくれているように感じます。このような会社は若手・ベテラン関係なく、どんな社員の意見も積極的に取り入れ、風通しが良く働きやすい環境であると考えているため、就職先の決め手としています。」
解説
ポイントは「仕事選びの軸」と「本当に入社する意思があるのか」です。まず仕事の選びの軸に関しては、もちろん自分が大切にしている軸とすり合わせることも大切ですが、その軸が応募先企業の軸とマッチしているか否かも見極めることが大切です。
また、決め手を面接で質問される場合、本当に入社する意思があるのか確かめたい側面もあるため、「○○な特徴があり」や「○○な雰囲気を感じたため」など具体的に自分が良いと思ったところを伝えることが大切です。
どうしても決められない時はプロと”一緒”に考える
就活エージェントの真骨頂は、あなたの悩みに寄り添いながらもあなた自身が潜在的に持っている答えを質問によって導いてあげることです。良いエージェントは答えを押し付けるのではなく、答えを引き出します。この場合も最終的に決めるのはあくまであなたです。
就活の方法や重要なポイントを押さえても、初めての経験でどうやって進めていけば良いのか分からず悩んでいる就活生も多いのではないでしょうか。
そんな時は就活エージェントに頼るのも有効だと言えます。なぜなら、就活エージェントの真骨頂は、あなたの悩みに寄り添いながらもあなた自身が潜在的に持っている答えを質問によって導き出せることだからです。
優秀なエージェントは答えを押し付けるのではなく、就活生の答えを引き出します。しかし就活エージェントが答えを引き出したからと言って、必ずしもその答えがあなたにとってベストだという保証はありません。最終的に決めるのはあくまであなた自身です。
そのため、就活エージェントの力を借りつつも、最終的に決めるのはあくまで自分自身であることを忘れないでください。
まとめ
今回は就職先の決め手や注意点などに関して解説しました。複数内定を持っているということは、各企業から「あなたが魅力的で、ぜひうちの会社で働いてほしい」と思われている証拠です。
しかし、本当に大変なのはどこの会社に就職するかを決めることです。そのため就職先の決め手となる軸をしっかり持つことが重要になります。
RANKING
人気記事ランキングTOPIC
新着記事